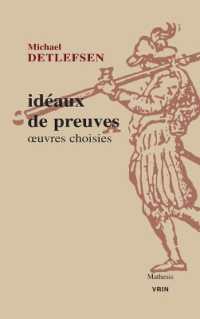内容説明
「墨」は作られた日から微妙に変化をつづけ、硯、水、紙との組み合わせで神秘的なまでに墨色を変えていく。実用品としての墨は三十年から五十年で最も冴えた墨色を示し、百年で鑑賞、愛玩用へと役目を変える。一方、紙にえがかれた墨の色は、千年たっても亡びることがない。こうした複雑な墨の特性を平易に説き、手作業による墨作りの様子や、著者愛用、愛玩の名墨の数々を紹介。軽妙な語りで「墨」の魅力を余すところなく伝える。
目次
墨の妖気
奈良を歩く
墨の起源
名墨について
墨の生成
油煙墨の艶
松煙墨の冴え
未来派アンソラセン
朱墨
あの墨この墨鑑賞〔ほか〕