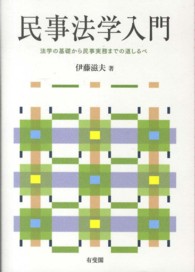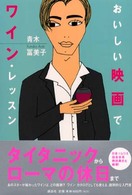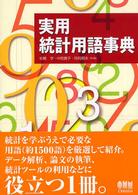内容説明
宮古島の「六月ニガイ」、宮崎県の「銀鏡神楽」、長野県の「遠山の霜月祭り」など、実際に見聞した日本各地の祭りや神楽、宗教的な儀礼や行法から、子どもの遊びといった日常の行為まで、具体例をあげながら、「自分と自分以外のものとの間の回路」としての「穴」をキーワードに、身体にいわば埋蔵された日本文化を解明する。「宗教」と「芸術」の隙間を思考する、独創的な論考。祭りを体験しながら、身体が変容する、現代の「変身物語」でもある。
目次
序章 からだに穴が開く
第1章 穴を発掘する
第2章 穴の“かたち”
第3章 穴の複合としての「祭り」
第4章 穴の射程
終章 “際”の思考から、“穴”の思考へ
著者等紹介
梅原賢一郎[ウメハラケンイチロウ]
1953年、京都市生まれ。1982年京都大学大学院文学研究科博士課程修了。専攻は美学・芸術学。現在、滋賀県立大学助教授。各地の祭りや儀礼などを探訪し、芸術や宗教について、身体を軸に、新しい視座から思索している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
1
カミの現象学 身体から見た文化論 「穴」 自己と外部の通路 身体的開口部超えた「穴」 奇跡的強度の「場」 何かが侵入する場 自発的な「やわらかい穴」 強制と努力の「硬直した穴」 宗教 穴開けの技法 人間 「穴を開ける動物」 外部に晒された自己の再認識 「穴の分布図」 現代社会で平板化 宗教への二つの錯誤 教義への偏重 「外部」の実体化 「穴」はすぐに消える 美術館は「政治的装置」 コンサートホールは「不自由な器」 「肉の裁ち直し」 身体の変容 「臍の緒」 世界との繋がり 神と人のコミュニケーション形式2025/05/23
takao
1
ふむ2024/10/04
青緑
1
久々に読んだノンフィクションの本。文章が読みやすくて面白い。P29の「外部のなにものかについては語ることができない。(中略)信じるか信じないかは不毛な問いである。」という部分に衝撃を受けた。そうか、それで良いのか、と。2019/06/24
umiumi
0
愛読書2007/09/29