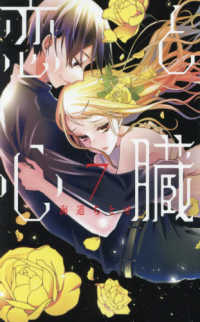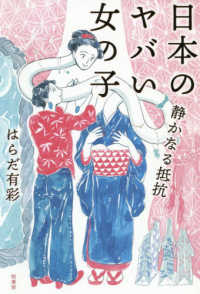出版社内容情報
滑稽猥雑を旨とする男系の文学・俳諧の世界へ女性俳人はいかに参入し、活躍の場を広げていったか。本書では、元禄期の女性俳人から近代的自我の覚醒を格調高く詠いあげた杉田久女まで三十余名の作品を鑑賞する。
内容説明
滑稽猥雑を旨とする男系の文学・俳諧の世界へ女性俳人はいかに登場し、活躍の場を広げていったか。本書では、元禄期の女性俳人から、近代的自我の覚醒を格調高く詠いあげた杉田久女まで、三十余名の作品を鑑賞する。男社会の軋轢のなかで句作を断念した人、志を抱きながら夭折した人、ハンセン病と闘いつつ生涯俳句を捨てなかった人、金融大恐慌の因をなした金子直吉の妻せん女など、俳句に命をかけた女性たちの凄絶なドラマ。
目次
元禄期の女性俳人(堀切実)
機知のひらめきと求道の心 捨女(金田房子)
蕉門の代表的女流俳人 園女(東聖子)
「女流」の眼差し 秋色(永田英理)
北陸の地に勁く慎ましやかに生きた女性 千代女(藤原マリ子)
滲み出る孤愁の思い 諸九尼(深沢了子)
奇蹟の星 星布(井上弘美)
自由闊達な文人尼 菊舎尼(清登典子)
陸奥の女流市原多代女 多代女(中野沙惠)
明治開化期の女性俳人(越後敬子)〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
元気伊勢子
5
久しぶりに俳句をやってみようかと思い、手に取ってみた。俳句って17文字と凝縮されているから小説よりもストレートに人間性が出るのかもしれないなんて思う。2022/04/06
かーんたや
1
秋色 もののふのもみぢにこりず女とは 井戸ばたの桜あぶなし酒の酔2021/01/09
麺
0
スコット沼蘋女の「騎士の鞭ふれてこぼるゝライラック」という句を偶然SNSで見かけ、同時代の他の女流俳句も読んでみたくなり購入した一冊。 俳人ひとりひとりを順に解説していく本で、時代は近世から始まる。(その頃の女性の句が残っているんだというのにまず驚いた) 虚子門下で多数の女性俳人が花開いたということで、そのあたりの人間関係も興味深く読んだ。 杉田久女の「土濡れて久女の庭に芽ぐむもの」は、その背景を知った後に読むと、その力強さと健気さに息を呑まれる。紹介されている俳句の中で1番好きかもしれない。2022/07/21