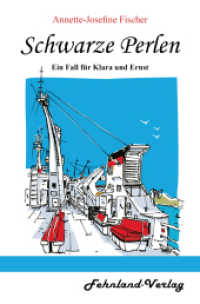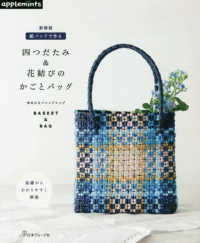出版社内容情報
彼らは本当に敗者だったのか?勝者の視点からは伝わらない古代史の真相戦中から60年以上研究をリードしてきた日本考古学界の第一人者が、記紀の中で<敗者>と記されている人物・一族を、それぞれの地域の歴史を掘り起こしながら、考古学・文献双方からアプローチする新視点。
森 浩一[モリ コウイチ]
考古学者、同志社大学名誉教授。昭和3年大阪市生まれ。同志社大学大学院文学研究科修士課程修了。旧制中学時代から橿原考古学研究所に出入りし、考古学と古代史の接点である古代学を専門とする。「地方の時代」や「古代ブーム」の推進者的存在で、学界最後の重鎮。著書多数。
内容説明
彼らは本当に「敗者」だったのか?第二次世界大戦中から考古学界に身を置き、60年以上にわたり研究をリードしてきた日本考古学界の第一人者が、記録のなかでは「敗れた」と記述されながら、実際には語り継がれ、ゆかりの地で神として崇められてきた事象を、考古学・文献双方からのアプローチで、新視点を提示。古代に敗れた人たちの姿を浮き彫りにする。
目次
饒速日命と長髄彦
タケハニヤス王とミマキイリ彦の戦争(前篇;後篇)
狭穂姫と狭穂彦
熊襲の八十梟帥と日本武
剱御子としての忍熊王
莵道稚郎子と大山守
飛騨の両面宿儺
墨江中王と曽婆訶理
大日下王と押木珠縵
市辺忍齒別王と皇子たち
筑紫君石井
物部守屋大連
崇峻天皇と蜂子皇子
山背大兄王と一族の死
蘇我氏四代―稲目、馬子、蝦夷、入鹿
有間皇子と塩屋連〓魚(しほやのむらじこのしろ)
大津皇子と高市皇子の運命―壬申の乱
大友皇子の死とその墓
著者等紹介
森浩一[モリコウイチ]
1928年大阪生まれ。同志社大学名誉教授。日本考古学・日本文化史専攻。同志社大学大学院修士課程修了。72年から同大学文学部教授。2013年6月、逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
-





ヒロの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
AICHAN
月をみるもの
雛子
moonanddai
dzuka
-
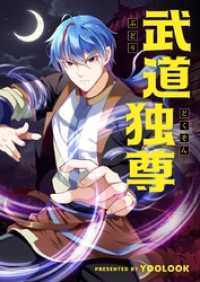
- 電子書籍
- 武道独尊【タテヨミ】第116話 pic…
-

- CD
- くるり/ハイウェイ