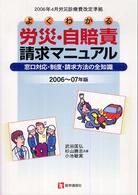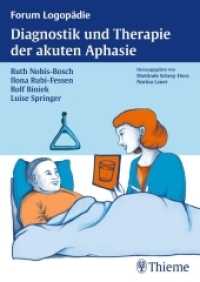内容説明
なぜ、自民党は長期にわたり政権を担当できたのか。戦後の出発から民主党政権崩壊まで含めた、歴代政権通史。
目次
プロローグ 戦後政治の概観と自民党
第1章 戦後民主化と政党活動の開始
第2章 自民党の誕生
第3章 高度経済成長の準備と安保闘争
第4章 高度経済成長の時代
第5章 安定成長への模索と田中支配
第6章 自民党の衰退、下野
第7章 五五年体制の崩壊
第8章 野党からふたたび与党へ
著者等紹介
小林英夫[コバヤシヒデオ]
1943年、東京生まれ。早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授。博士(文学)。専攻はアジア経済論/植民地の経済史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
19
派閥。宏池会、清話会、平成研究会(22頁)。お仲間、お友達集団。中曽根はその他か。アジア問題調査会には小泉信三を介して、赤松要、山本登、板垣與一、原覚天、大来佐武郎という新進気鋭の学者や官僚が結集(91頁)。池田内閣の月給2倍論(103頁)は現代の非正規雇用にこそ必要で、そうなれば多少は世の中安定するものの、アベノミクスではあかーん。中曽根は’41年東京帝大法学部卒。内務省入省。国防費対GDP比1%の見直しに、‘85年8月靖国神社公式参拝でアジア各国から批判(139頁)。プラザ合意で円高ドル安。 2014/12/31
西澤 隆
5
自分がリアルタイムに遭遇していない時代のひとのことを読んでいた前半部では「教科書のようなさらっとしたまとめだな」と思う。でもだんだん今に近づき、知っている政治家が登場するようになってくると「へえこの人をこう酷評するのか」など筆者の色が見えてくる。じゃ、きっと昔のひとたちのこともいろいろ賛否の分かれることを書いているんだろうなと想像したり(笑)。この手の本では失策の批判はある種の定番。もうすこし「この時打ったこの手が後で効いてきた」的な政局に紛れて見えにくい「いい政治決断」を読みたかったなという気がします。2019/07/03
スズツキ
4
概要を知るにはグッド。2014/06/02
スプリント
3
戦後の自民党結党前から民主党から政権を奪還した後の安倍政権までを網羅しています。コンパクトにまとまっていることもあり全体の流れを理解するには最適です。派閥の系譜をみると現在の派閥のトップに個性もカリスマもないことに驚かされます。2014/04/03
百木
1
55年体制の成立から政権の中枢にあり続けた自民党の党史を「派閥」の変遷と変容にスポットを当て通史的に追った内容。内容としては概要的なレベルに留まるのでざっと知りたい人向け。政争の結果が我が身に降りかかると思うと多少なりともアレですけど一歩引いて見ると時折交えられるエピソードなんか結構面白いジャンルですね。あんまり読まないジャンルなので新鮮でした。2017/06/16