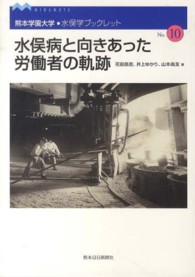出版社内容情報
人々が高度経済成長に沸くころ、太郎の眼差しは日本の奥地へと向けられていた。恐山、津軽、出羽三山、広島、熊野、高野山を経て、京都の密教寺院へ――。現代日本人を根底で動かす「神秘」の実像を探る旅。
内容説明
「日本人としての存在を徹底してつかまないかぎり、世界を正しく見わたすことはできない。」人々が経済成長と五輪に沸くころ、太郎の眼差しは日本の奥地へと向けられていた。下北、津軽、出羽三山、広島、熊野、高野山を経て京都の密教寺院へ。聖地で目のあたりにした祭りや人々の姿は、日本人を深い底で動かす「見えない暗号」としての“神秘”の力を印象づけるものだった。カメラを手に踏破した日本最深部への旅。
目次
オシラの魂―東北文化論
修験の夜―出羽三山
花田植―農事のエロティスム
火、水、海賊―熊野文化論
秘密荘厳
曼陀羅頌
著者等紹介
岡本太郎[オカモトタロウ]
1911年生まれ。29年に渡仏し、抽象芸術運動に参加。パリ大学で哲学、社会学、民族学を学び、ジョルジュ・バタイユらと活動をともにした。40年に帰国し、戦後、前衛芸術運動を展開。70年、大阪万博で“太陽の塔”を制作。さまざまなメディアで発言を続け、「芸術は爆発だ!」などの名言を残した。1996年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
47
1960年代に神秘的習俗を訪ねたレポート。イタコなど青森の祭祀は、虐げられてきた女性が自らを救済する呪術。各自が生命を爆発させる事を救済としてきた著者は、ここで芸術と呪術のつながりに注目する。出羽三山では、平地を追われた先住文化の名残りを修験道の中に探す。求めるのは芸術の閉塞を打ち破るヒント。議論は密教とマンダラの章で一気に深まる。残念ながら、「見せながら秘密を孕むのが芸術」という論考は理解不十分。現代芸術が、直接的なようで実は「作品」に固執しているという指摘は鋭い。著者撮影の写真も見応えあり。2020/09/15
no.ma
21
恐山、出羽三山、そして熊野。岡本太郎は現地に足を運び、神社やお寺の形式・儀式で厚くおおわれて目隠しされている、信仰のプリミティブなエネルギーを感じとる。それは神秘の実感であり、日本人の思考、モラルを深い底で動かしているものだ。解説の中沢新一がいうように、切れ味のよい見事な文章は、論理に一貫性があって、すこしもブレがない。対象にたいするいやらしい媚など微塵も感じられない。私も太郎スピリットでいこうと思う。「結論的に言おう。宗教も芸術も、秘密であることによってのみ、そのものであり得る」。2022/02/19
ロビン
18
青森は津軽のオシラやイタコ、山形の出羽三山の修験、広島と島根にまたがる地域の花田植、熊野三山、高野山の密教と曼荼羅・・岡本太郎が日本の初源的な信仰の呪力、その秘密を探求した一冊。『日本再発見』よりも更に民族学的な内容であり、高度な芸術文化論が展開され、難解であった。東北文化を語るなかで「女の力こそ、貧しい日本、その運命を、顕彰されないまま黙々と支えてきた。久しい歴史の間、底の底で。」と語り、東北のお婆さんに象徴される女性の運命に思いをはせる太郎の優しさが沁み、曼荼羅から語られる芸術観の厳しさにも打たれる。2022/07/16
ぜんこう
16
オシラの魂(東北文化論)、修験の夜(出羽三山)、花田植(農事のエロティスム)、火・水・海賊(熊野文化論)、秘密荘厳、曼荼羅頌---岡本太郎が日本各地の神秘をめぐって、自分で感じたことを記したルポみたいな感じでしょうか。 岡本太郎氏がこんなに整然とした文章を書いていることに驚きました。また、自分の考えがビシッとぶれることなく客観的に物事を見ているのが氏らしいです。 ちょっと哲学的な感じで、僕には読みにくかったですが、岡本太郎氏の作品以外の一面を見ることができました。2015/10/10
roughfractus02
8
修験道や天台・真言の早駆けのような文体は、弥生以後の平地の文化によって山岳に追いやられた縄文の痕跡を求めるように、現代日本の意識の表層から深層に降りていく。その違いを、護摩の火を見つつ視覚に訴える夜の火と触覚に訴える昼の火に重ねる著者は、その跡を下北や出羽の山岳から広島、熊野を経て平地文化の中心京都の密教へと辿る。「ひらくべくして、ひらかなかった魂」とされる古層は五感を超えた「神秘」ではない。ものと自我に距離を作って固定する視聴覚的な世界の中で、瞬間瞬間に消える嗅・味・触覚的な世界である(1964刊)。2023/03/20
-
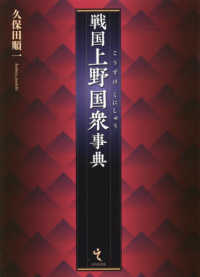
- 和書
- 戦国上野国衆事典