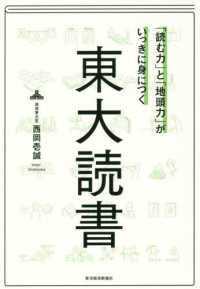内容説明
戦国武将・大名として信長・秀吉・家康の3人の天下人に仕え、「へうげもの」(剽軽な物)をとりこんで乱世を生きた古田織部。その名は「織部焼」として世に知られるが、実際に何をなした人物だったのか謎も多い。千利休の跡を継ぐ茶の湯の天下一宗匠として、慶長年間の茶の湯を変革。斬新・豪放な造形の織部焼をコーディネートし、新奇の流行を巻き起こした茶人・織部に焦点を結び、桃山文化を演出した奇才の実像を活写する。
目次
第1章 古田織部の生き方(エピソードで探る織部の評判;茶の湯宗匠スターダムに昇る ほか)
第2章 古田織部の指導力(古田織部の指導力;織部の創造力の拠り所 ほか)
第3章 織部と創作陶芸(古田織部と新作茶陶;唐津焼をめぐる織部の役割 ほか)
第4章 茶道具に注がれた織部の創意(ケース・バイ・ケースの創意;茶碗に示す織部の個性 ほか)
第5章 織部の茶の湯変革(食器革命と織部;創作食器と酒器 ほか)
著者等紹介
矢部良明[ヤベヨシアキ]
1943年生まれ。東北大学文学部美術史科修了。東京国立博物館陶磁室長・同考古課長・同工芸課長、郡山市立美術館館長を経て、現在、人間国宝美術館館長。専門は茶道史、中国・日本陶磁史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 洋書電子書籍
-
リーダーシップの主要概念
Lea…


![鈴木英人ポストカードブック Musics [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47683/4768317022.jpg)