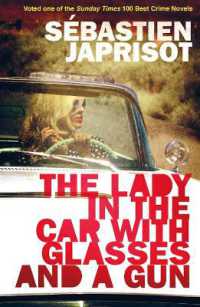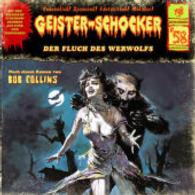出版社内容情報
野心に燃える貴族や武士が鎬を削り、覇者・清盛を生んだ兵乱の真実に迫る!
貴族から武士へ。古代末期の二つの兵乱、保元・平治の乱を画期として、時代の主役は移り変わってゆく。武士を両兵乱の主人公とする通説に挑み、王家・摂関家・新興貴族・武士が複雑に絡みあう政争の真実を描き出す。
内容説明
貴族社会が崩壊を迎える平安末期、京を舞台に勃発した保元・平治の乱。武士中心に語られてきた通説は、錯綜する兵乱の真実を本当に捉えているのか。河内源氏と伊勢平氏を巻き込み、王家と摂関家が骨肉の争いを繰り広げた保元の乱。政治の実権を握った信西を、院近臣藤原信頼らが源義朝の武力で倒すも、平清盛に敗北、河内源氏の壊滅と清盛の勝利を招いた平治の乱―。野心に燃える貴族と武士たちが鎬を削った、闘いの真実に迫る。
目次
第1章 分裂する政界―鳥羽院政期の政情
第2章 帝王と上皇―保元の乱の勃発
第3章 激闘の果て―保元の乱の結果
第4章 新たな闘い―平治の乱の前提
第5章 闘いの終息―平治の乱の結末
むすび 武者の世の到来
著者等紹介
元木泰雄[モトキヤスオ]
1954年、兵庫県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程指導認定退学。中世前期政治史専攻。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。京都大学博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ほうすう
15
この時代に関してはかなり不案内であり、うっすらとした教科書の知識と大河の「平清盛」の知識ぐらいしかなかった。そのために読んでいて新鮮な気持ちで色々と知ることができた。武士の世の始まりともいわれる二大戦闘も摂関家内部や院の近臣間での対立があくまでも主であり、武士は少なくとも主体的に乱に関わっていってないの様子。特に清盛に関しては最終的に勝者になった割に戦乱に乗り気でなかったらしいこと、乱以前も崇徳上皇に近い存在であり、後白河や信西と近い関わりでもなかったということなど意外であった。2020/04/21
オルレアンの聖たぬき
6
保元の乱、平治の乱は、教科書通りに理解すれば、平清盛率いる平氏一門が『平氏にあらざれば』の時代を築くためのきっかけになった事件だと理解していたが、実相は全く違った。他の日本史の英雄がそうだったように時運に乗れる幸運を持ち合わせていたのが一つの理由。両乱とも、摂関家と王権の混乱から生じたものというのが大半の理由だった。2023/07/30
失速男
4
摂関家が没落、院政がしかれ、武家が台頭してくる怒濤の時代。姻戚関係や官位などから人間関係を解きほぐし、すさまじい権力闘争の果ての乱であることがよくわかる。しかし当時の貴族はどいつもこいつも男色が趣味って、、、、2017/04/26
いきもの
4
保元・平治の乱といえば源義朝、平清盛が活躍した戦というイメージが強かったが、院政・摂関家の対立や、台頭した院近臣などが複雑に絡み合った戦であったというのがなかなか興味深かった。ここで飛躍した清盛もそれぞれの乱にそれほど積極的に関与しておらず、中立的な位置にいることが多かったのが意外。清盛のライバルとして描かれることの多い義朝も、清盛に比べれば身分はだいぶ低く、東国で形成した軍事力を背景に乱の中心にいたというのも意外であった。藤原信頼が清盛の先駆的な人物として注目されていてこれまた興味深かった。2015/08/09
katashin86
3
著者の講義を受けたのももう10年以上前になるが、それまでの自分の通説的な理解から蒙を啓かれたと感じた印象は強く残っている。 初版2004年、この本の内容はそのまま講義されていたはず。平氏一人勝ちとなった平治の乱より、院政権門として確立した王家・摂関家がそれぞれ内紛・衝突しついに崩壊・無力化する保元の乱こそが時代の画期であることが改めて理解できた。2022/10/07
-

- 電子書籍
- 鋼兵の整備士(2) BLIC
-
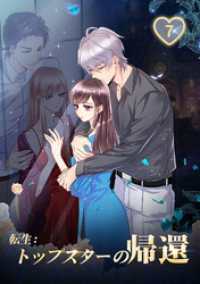
- 電子書籍
- 転生:トップスターの帰還第7話【タテヨ…