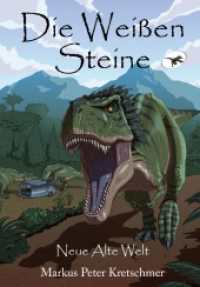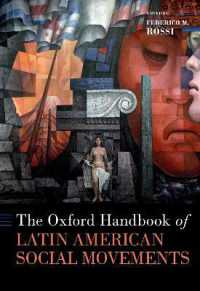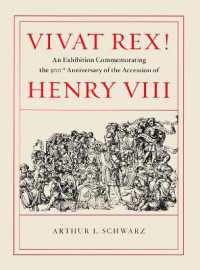内容説明
「心がひきおこすこういったさまざまな現象に、適切な理解線をみつけだし、何とかして統一的に、心の動きをつかまえたい」。心的世界をどうとらえるか。心を理解する上で必要な方向軸とはなにか―。自らの問いの答えを求める孤独な試みの果て、時に「人間というものの不可解さと悲しさにたちすくみ」ながら到達した、吉本隆明の代表作。
目次
1 心的世界の叙述
2 心的世界をどうとらえるか
3 心的世界の動態化
4 心的現象としての感情
5 心的現象としての発語および失語
6 心的現象としての夢
7 心像論
著者等紹介
吉本隆明[ヨシモトタカアキ]
1924年、東京・月島に生まれる。47年、東京工業大学電気化学科を卒業。詩人、文芸評論家、思想家。52年、詩集『固有時との対話』を発行。その後、文芸評論活動を開始する。思想家として、戦後日本の思想界に大きな影響を与えた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yutaro sata
33
世界からも自分の身体からも疎外されている場所、原生的疎外の場所に心的領域を定め、異常や病を、心的領域の、時間や空間との一次的対応の様相から見ていく。 『共同幻想論』同様、フロイトの仕事をどう批判的に発展させていくかが大きなテーマとなっているように思う。 感情が、なぜ空間とより関わるのかなどは、いまだよく消化できず。じっくり行こう。 夢を、既視の夢、固有夢、一般夢というように分けていけば、あらゆる夢を解釈可能性として考えることができる、などという箇所は面白い。 これはまだ序説であって、私は本論へ向かう。2023/11/28
yutaro sata
19
読むのは3回目か。『本論』を読み終えてから読むのは初めて。夢の話が1番面白いかなあという感想は変わらずかな。この何年かで理解がすごく進んだという感じでもなく、まあそこは焦らず行くしかないが、とりあえず宇田亮一さんの読み方本に進んでみる。2024/08/27
またの名
9
日本語でおk。極めて鋭い言語感覚で書かれた探求に対してそう言わざるを得ないのは、あまりに鋭く独自過ぎる思想体系から繰り出される純粋・原生的疎外、了解と関係の三つ組等の概念がハンパなく理解し辛いから。鍵となる時間と空間の定義も明確でなくて混乱が増すけれど、フロイトと対決しつつ夢を論じる個所で時空間をモチーフに心的現象を分析してきたことの意義が氷解し、想像力や共同幻想への接続を暗示しながら終わる結末を読む頃には、ドンキホーテ的蛮勇に感服している。分裂病・失語症論が意味不明で成否を判じ得なくてももう仕方ないか。2013/12/20
なつのおすすめあにめ
5
解題に引用されている柄谷行人の書評は「大衆と知識人」と、お馴染みのモチーフを使っていて面白い。はしがきとあとがき(全著作集と角川文庫版の3つともすべて)に書かれてある決意は力強い。しかし『心的現象論・本論』を読んでも完成していないと書かれたレビューや、Ⅱ-2までの内容とそれ以降の内容が合わないとも書かれていた事、フロイト批判している箇所はなんとなく理解できた気がするのですが、この本は『心的現象論序説 』。そう、あくまで「序説 」。難解とされる『共同幻想論』よりも難解なのは未完成……だからなのかもしれない。2026/01/11
yutaro sata
2
これはとびきり難しい。最近本論が出たようですけれども序論を消化するのにどれくらいかかるものか。本論に飛び込んだ方が良いのか。2022/04/24
-

- DVD
- アヴェ・マリアのガンマン