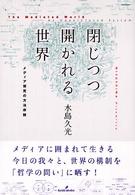内容説明
訓読みは、発音も概念も文法も全く異なる中国語の漢字を受け入れ、それを大和言葉で読むことに始まった。以来、日本人は、漢字の読みとしてだけでなく、英語や洋数字、さらには絵文字を日本語に取り入れる際にも、訓読みの手法を発揮した。日本人が独自の感性による創造を加えながら、各時代の中で発展させてきた訓読みは、今も自在に変容し続けている。そのユニークな例を辿り、豊かで深遠な日本語の世界に分け入る。
目次
第1章 訓読みの歴史
第2章 音読みと訓読み
第3章 多彩な訓読み
第4章 訓読みの背景
第5章 同訓異字のはなし
第6章 一字多訓のはなし
第7章 漢字政策と訓読み
第8章 東アジア世界の訓読み
著者等紹介
笹原宏之[ササハラヒロユキ]
1965年、東京都生まれ。早稲田大学第一文学部で中国語学を専攻、同大学院文学研究科では日本語学を専攻。博士(文学)。早稲田大学社会科学総合学術院教授。経済産業省の「JIS漢字」、法務省法制審議会の「人名用漢字」、文部科学省文化審議会の「常用漢字」の改正にも携わる。『国字の位相と展開』(三省堂)により第35回金田一京助博士記念賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モリータ
11
◆2008年光文社新書刊、2014年角川文庫刊。著者は1965年生、早稲田大学教授。メディア等でもおなじみの通り「漢字博士」である。政府の漢字政策(経産省のJIS漢字、法務省の人名用漢字、文科省の常用漢字)にも携わる(縦割りだなぁ…)。◆概説としては1章(訓読みの歴史)、2章(音読みと訓読み)、3章(多彩な訓読み)、7章(漢字政策と訓読み)。あとは豊富な具体例という感じ。2022/07/04
isao_key
11
普段あまり気にかけない漢字の音訓読み。日本人が大和言葉で読むために発明した訓読みについて書かれた本。タイトルも秀逸。あまり知らされていない、漢字の読み方が多く紹介されていて、漢字の薀蓄を知るにはもってこいの本。雨の日に着る「カッパ」の「合羽」は、ポルトガル語源で、「ガラス」の「硝子」はオランダ語からの当て字。「御転婆」もオランダ語起源だという説もあるらしい。十月十日は、以前は「朝」が組み合わされていると覚えたが、今は「萌」で、この日は「萌えの日」だという。「風邪」も江戸時代は「フウジャ」と読んでいた。2015/06/28
shou
8
訓読みについて、漢字文化と和語の出会いの歴史からネットスラング、外国語との差異や訓読みの問題点まで、広く柔軟に取り上げた内容。「Wる」なんて言葉の成立過程まで考察する、言葉へのあくなき好奇心を感じる。2015/02/25
HMax
6
小ネタ満載で楽しめました。日本語では漢字の意味が重要で、読みは訓読みがあるため、同じ文字の読みが時代とともに変わる。なるほど。 韓国では時計等、日本語の漢字語が多く入っているのは知っていましたが、中国でも「混凝土」「場所」「場合」のように逆輸入されているものが多かったんですね。 そういえば人民・共和国も日本語由来でした。2016/05/14
endocco
6
高校生へのネタ本に最適。一部評論文として教材にしたり、自分で身近な例を探させるのもいいだろうと思う。筆者が蓄積してきた広範な用例がさりげなく語られているのだけれど、これは並大抵のことではない。一冊を通して体系的に主張がまとまっているわけではないが、だからこそ「訓読み」の多様性と複雑さを実感できる。2014/05/27