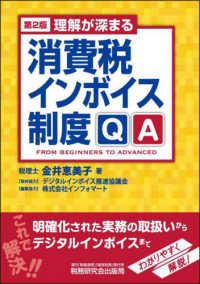内容説明
昭和19年、鈴木大拙は軍部が宣揚する日本精神に対抗して日本的霊性を唱え、本書を著した。大拙は精神の根底には霊性(宗教意識)があると主張。鎌倉時代の浄土系宗教と禅宗を重視した。念仏や禅の本質を生活と結びつけ、わかりやすい言葉で読み解き、日本人が持つべき心の支柱を熱く語る代表作。大拙は戦後、長文の序を付け再刊し、霊性の主張を本格始動した。本書はこの2版を底本とした〔完全版〕。
目次
第1篇 鎌倉時代と日本的霊性(情性的生活;日本的霊性の自覚)
第2篇 日本的霊性の顕現(日本的霊性の胎動と仏教;霊性;日本的霊性の主体性)
第3篇 法然上人と念仏称名(平家の没落;浄土系思想の様相;念仏と「文盲」;念仏唱名)
第4篇 妙好人(赤尾の道宗;浅原才市)
第5篇 金剛経の禅(般若即非の論理;「応無所住而生其心」;三世心不可得;禅概観)
著者等紹介
鈴木大拙[スズキダイセツ]
本名、貞太郎。1870年、金沢市生まれ。東京帝国大学在学中に、円覚寺にて参禅し、大拙の道号を受ける。97年、渡米。『禅と日本文化』(英文)を発表。帰国後、学習院、東京帝国大学、大谷大学で教鞭を執るほか、英文雑誌を創刊し、海外に仏教や禅思想を発信した。1936年、世界信仰大会に日本代表として出席。イギリス、アメリカの諸大学で教壇に立った。66年、没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
52
哲学同好会の読書会でのテキスト。哲学というと、普遍的な内容を扱っていて、時代性など関わりがないと思っていたが、戦時中に書かれた本書は、時局のあり方、当時の大拙の置かれた立場などが微妙に影響していると感じた。完全版と称する本書は、第五篇で「金剛経の禅」を扱っているが、レポート当番になり苦心惨憺。所謂「即非の論理」については、未だ解明するに至らず。残された時間も不確かな中、このような言語遊戯(失礼!)に身をやつしている暇はないのだと思ったりもする。読書メーターに本書を登録された皆さんの感想を拝見すると、難しい2024/12/24
to boy
22
難解な内容で、何度も読み返しながら読んだので時間がかかってしまいました。精神と言うと物質の反語となって二元論となってしまうので、それを超越した霊性を考えしかも日本固有のものを考察してますが、難しい。4章の妙好人は面白かった。才一の詠う念仏がなぜか心に沁みてきます。第五章は超難解でほとんど理解できませんでした。2016/04/17
koji
18
コロナ禍の中、「苦から救済する」仏教の教えは、祈りと言葉で日本人の精神的支柱になりうるのではないかという問題意識の下、読み始めました。解を求める浅はかさを大拙先生になじられているように感じながらも、愚直に読み進めた所、第5章で次の言葉にでくわしました。「(他人に迷惑をかけないという前提の下)結果が自分にとってどういうことになるかは気にせず、働くことそのことに意識の全力を傾注するのが大切。」所謂、無功徳無報償の行動です。「大地に根ざす、超個、即非の理」より無功徳が、私の心にピタリときて、勇気を貰いました。2020/04/17
nomak
17
戦時中に執筆した大拙はすごい。止むに止まれぬ想いを感じた。これはすごく遠回しな戦争批判。天皇を神とした国家主義な神道への批判だ。禅と浄土とゆう日本のガラパゴス仏教が生まれたが、日本人に浸透するまでは時間が足らずに、国家主義神道へのアシストになり天皇と英霊を信じて戦争へと突き進んでいった日本人の姿が大拙にはたまらなかったことだろう。良くも悪くも島国ディフェンスによって日本人が長い間外敵とは無縁であったために精神が育ったなかった。大地に叩きつけられて霊性があり、大地性が必要だと繰り返している点に感銘を受けた。2020/09/23
Gokkey
14
第二次大戦前の神道的思想に対するアンチテーゼ、より深い存在論的考察に基づいた「日本人であること」の本質を問う。これを霊性と定義し、様々な角度から考察を進める。大拙によれば、霊性とは精神よりも高次にある無分別智であり、この上に宗教意識が鎮座する事で民族文化が形作られる。大拙は禅こそが日本的霊性顕現のトリガーとし、「ひとえに親鸞一人になりにけり」に換言される一人一人の個の具体即実在性に辿り着く。この主客超越的な存在論から後半部にかけて様々な論考を展開するが、どうも今一つ整理されておらず理解に苦しむ。2023/07/08