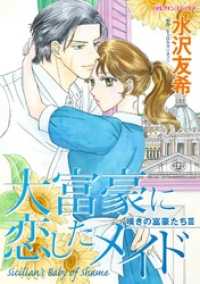内容説明
楊貴妃は豊満が美しいとされた唐代の美女の典型だった。剃り落とした眉にお歯黒が江戸の美女なら、同時代の清王朝では纏足が美人の条件だった。なにを美しいと感じ、醜いとするか、美人という基準は時代や文化によって違い、多くの謎を含んでいる。文学や絵画に描かれた美女のイメージ、化けて出る美女という異文化に共通する要素の不思議など、比較文化の視点から日中美人像の移り変わりを追い、「美女という幻想」に迫る。
目次
プロローグ 美女とは何か
第1章 好まれた美貌
第2章 恐れられた美女
第3章 図像の修辞法
第4章 作り出された美貌
第5章 漢詩文のなかの美人、和文のなかの美人
第6章 審美観の交響
第7章 江戸文化のフィルター
第8章 ナオミが誕生するまで
エピローグ 美貌のゆくえ
著者等紹介
張競[チョウキョウ]
1953年、中国上海生まれ。明治大学教授。上海の華東師範大学を卒業、同大学助手を経て日本留学。東京大学大学院総合文化研究科比較文化博士課程修了。専攻は比較文化論。主な著作に『近代中国と「恋愛」の発見―西洋の衝撃と日中文学交流』(岩波書店、1995年度サントリー学芸賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Chicken Book
9
ダーウィンは「人体の美について何か普遍的な標準が人間の心の中にあるという事は、確かに真実でない」と言ったらしいが、それを日中の文学作品における「美人」の表象から読み取ることができる。美しいかどうかを決めるのは、その顔・体をもつ本人ではなく、いつも他者である。どんな顔が、どんな体が美しいかは文化の影響を常に受ける。日本にも歯を黒くし、ふくよかな体が良いとされてきた歴史、ガングロが流行った時代がある。現在コンビニの雑誌コーナーに並ぶ水着の姉ちゃんを絶対的な美であるとするのには批判的にならないといけない。2021/11/03
明智紫苑
5
齋藤孝氏の3色ボールペン方式でチェックしながら読んでいたのを途中でやめてしばらく経ってから再読して、ようやっと読了。それくらい「美人」「美女」とは奥深く難儀なテーマなのだ。ヒエラルキーやレイシズムなどの社会的問題との関連性が強いテーマなのだ。「美人」とは理想主義の象徴だが、それに対して「不美人」とは現実の厳しさを象徴する存在なのである。何らかの「理想」を擬人化する際に、それをわざわざ「不美人」として描写する人は十中八九いないだろう。あと、「人形」などの立体物についての言及がもっとほしかった。2024/11/14
眉毛ごもら
3
日本と中国の美人観を詩歌と絵画などから読み取る本。各時代の化粧法についてや、美人の流行りの時代変遷など書いてあり面白い。漫画等も絵柄の流行り廃りがあるように美人観もだいぶ変遷がある。唐だけに唐突なデブ専ブーム的とかあの時代面白い。唐時代の服は可愛くて好き。日本の美人観は大陸からの影響は多少あれど和風ナイズに落とし込まれたり取捨選択したりと素直に入ってきてはいないようで独特なお歯黒やら眉剃りやらは断固として続けてたようだ。面白い本だった。2019/08/24