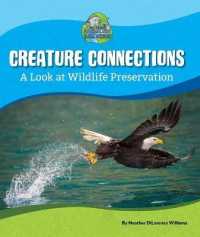内容説明
「橋」は「端」でもあり、異なる性格の地域と地域が接触する場所が「はし」であった。「橋」が架けられたことで、その両岸の「端」が「はし」でなくなり、広い地域を形成していく。水の都・江戸という大都会の生活に、橋はなくてはならない重要な都市施設だった。機械などのない時代、どんな道具や材料そして技術を使い橋は架けられたのか?江戸の橋の作られ方を徹底研究。江戸のモノづくりの技術と知恵が満載の1冊。
目次
第1章 隅田川の橋
第2章 橋はどのように造られたか
第3章 日本橋界隈の橋
第4章 堀と橋
第5章 銀座界隈の橋
第6章 橋の昔と今
著者等紹介
鈴木理生[スズキマサオ]
1926年東京生まれ。千代田図書館勤務を経て、東京都市史研究所理事。都市史研究家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。