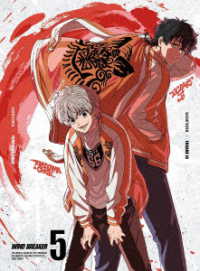内容説明
激情型の小野篁、女好きな在原業平、何ごとにも秀でた大納言公任、単純な陽成院…。王朝時代を彩る百人一首の作者たちは百人百様だ。王朝和歌の碩学が、『古今集』『後撰集』『大鏡』などに描かれる人間模様や史実、説話を読み解きながら、作者の新たな魅力を紹介。歌だけではうかがい知れない、百人一首の雅な世界へと誘う。作者の心に触れ、百人一首をより深く味わうエッセイ。
目次
序章 王朝文化の系譜―百人一首とはいかなるものか
1章 万葉歌人の変貌―人間化と神化と
2章 敗北の帝王―陽成院・三条院・崇徳院
3章 賜姓王氏の運命―良岑父子と在原兄弟
4章 古代氏族の没落―小野氏と紀氏と
5章 藤氏栄華のかげに―夭折の貴公子たち
6章 訴嘆の歌と機智の歌―文人と女房の明暗
7章 遁世者の数奇―能因より西行へ
終章 定家と後鳥羽院―百人一首の成立
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
40
本書は、「王朝時代を彩る百人百様の作者たち。親子・恋人・ライバル・師弟などが交差する人間模様を、史実や説話をもとに丹念に解きほぐす」というもの。ある意味ポピュラー過ぎるほどに馴染まれている(?)『百人一首』。だが、目崎氏も指摘されるように、「編纂直後から早々と忘却の羽目に陥り、千年もの長い間冬眠しつづけていた『万葉集』などは物の数でもない。」「すべての文化領域の典拠となり基礎となったのは、王朝の勅撰和歌だった。」そのエッセンスが『百人一首』。2025/04/11
やいっち
23
従前のありがちな百人一首本と違う。本格的。安直な読みやすいカラフルな本じゃ、和歌に絡む奥深い世界は素通りだなって感じている。その分、ささっとは読み通せなかった。 『応仁の乱』ではないが、自分のような素養のないものには、多くは高名な歌人・公家らなのだろうが、名前が読めない場合が多い(ルビは随所で…党外の人物が扱われた段階で振ってあるのだが、頁を少々捲ると、もう忘れてしまう)。2017/04/09
かふ
20
「百人一首」の入門書だと思ったら結構内容が濃かった。一人一人の和歌に加えてその背景となる物語に言及して、系統も錯綜としているからじっくり読み込む必要がある。その中で芭蕉や民俗学の柳田や折口まで広げていくのだからかなり豊富な知識を求められる。それでも百人一首の成立過程を描いたエピソードが面白い。すでに武士の時代が台頭してきて、権力闘争に敗れていく皇族や大貴族の末裔たちが、かつての「雅」な宮廷生活(青春の恋愛時代)を夢見て、それを自然の花鳥風月に重ねた藤原定家が後鳥羽上皇や「失われた時を求めて」という感じだ。2020/12/13
❁Lei❁
17
百人一首を足がかりに、平安時代の文化を俯瞰してみようという一冊。没落していった氏族や、不遇だった藤原氏の貴族、僧侶、女房などと分類され、それぞれの歌人が有機的につながるように解説されています。特に勉強になったのは、和歌と生活がもともと密着していたのに、時代を下ると題詠が増えていくことです。即興の面白さや感情のほとばしりが失われ、技巧が凝らされ芸術的に完成された歌ばかりになります。個人的に後半の歌の印象が薄いのは、詞書から垣間見られるドラマが少ないからかもしれません。玄人向けの、理解が深まる一冊です。2025/02/22
Mijas
17
正月といえば、百人一首で遊んだことを思い出す。歌の作者名も何となく覚えたものだった。本書はそうした作者を天皇、文人、古代氏族、女房、坊主などのカテゴリーに分けているので、坊主めくり以外にも天皇めくり、文人めくりなどの参考にできそうだ。内容は、文学史における400年間の王朝文化の検証である。他の史料も多々引用されていたので、丹念に読む必要があった。政治的敗者が自分の生き方の証として歌を詠んだり、和歌というものが当時の社会で必然的に生まれたものだということがわかる。日本の文化レベルの高さを改めて感じた。2015/01/04
-

- 電子書籍
- エボニー【タテヨミ】第4話 picco…