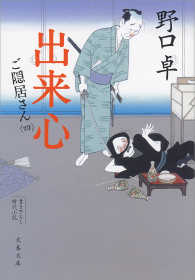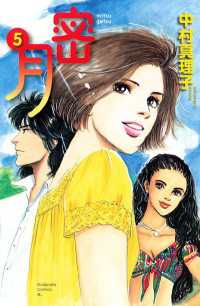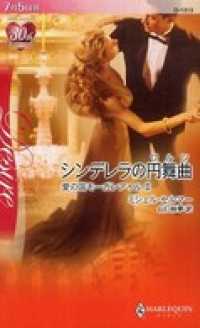内容説明
漢詩や酒を愛し、都鄙に遊びオリジナルな句を詠む。そうして生涯に残した発句は2850余句。本書では発句から蕪村の生涯をたどり、変幻自在な作風、現代からみても魅力的、四季それぞれの楽しみを味わえる、という基準で新たに1000句を選び年代順に配列。己と自然を一体化させてゆく芭蕉とは対照的に、画と俳諧の二つの道に生き、言葉によって理想郷を紡ぎ出し、時空をも超えた蕪村句の魅力に迫る。俳句実作にも大いに役立つ。
目次
元文二年(一七三七)丁巳二二歳
元文三年(一七三八)戊午二三歳
元文四年(一七三九)己未二四歳
元文五年(一七四〇)庚申二五歳
寛保二年(一七四二)壬戌二七歳
寛保三年(一七四三)発亥二八歳
延享元年(一七四四)甲子二九歳
元文二年(一七三七)~寛延三年(一七五〇)二二歳~三五歳
宝暦元年(一七五一)辛未三六歳
宝暦二年(一七五二)壬申三七歳〔ほか〕
著者等紹介
与謝蕪村[ヨサブソン]
1716‐1783年。江戸時代中期の俳人・画人。摂津国東成郡毛馬村に生まれ、若き日に江戸へ下向、以後関東・東北地方を遊歴して、画と俳諧を修業。36歳で帰阪して、丹後・四国地方を画家として歴訪、京都に定住した。55歳で夜半亭を継いで宗匠立机。俳句と画が映発し合い交響する「はいかい物之草画」(俳画)を創成する
玉城司[タマキツカサ]
長野県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科修士課程単位取得。文学修士。清泉女学院大学教授。専攻は近世俳諧史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ikedama99
feodor
shou
圓(まどか)🐦@多忙のためほぼ休止中
こ86