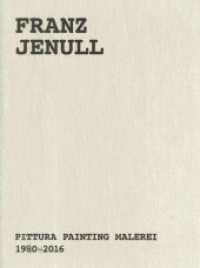出版社内容情報
固有名詞にとらわれることなく、われわれの眼前にでては消える事実によって、立派に歴史は書ける──。衣服、食物、家、風景、交通、酒、恋愛、職業と労働、貧と病など、「生活の横断面」による現代史の記述に挑んだ実験。詳細な注と解説、初版時の写真を収めた新訂版。
内容説明
固有名詞にとらわれることなく、われわれの眼前にでては消える事実によって、立派に歴史は書ける―。衣服、食物、家、風景、交通、酒、恋愛、職業と労働、貧と病など、「生活の横断面」による現代史の記述に挑んだ実験。詳細な注と解説、初版時の写真を収めた新訂版。
目次
第1章 眼に映ずる世相
第2章 食物の個人自由
第3章 家と住心地
第4章 風光推移
第5章 故郷異郷
第6章 新交通と文化輸送者
第7章 酒
第8章 恋愛技術の消長
第9章 家永続の願い
第10章 生産と商業
第11章 労力の配賦
第12章 貧と病
第13章 伴を慕う心
第14章 群を抜く力
第15章 生活改善の目標
著者等紹介
柳田国男[ヤナギタクニオ]
1875年、兵庫生まれ。1900年、東京帝国大学法科大学卒。農商務省に入り、法制局参事官、貴族院書記官長などを歴任。35年、民間伝承の会(のち日本民俗学会)を創始し、雑誌「民間伝承」を刊行、日本民俗学の独自の立場を確立。51年、文化勲章受章。62年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
9
歴史から見れば民俗学は現在の習慣に関わる学に見える。が、習慣はアリが地中を掘り進むように個々の行為によって世界の表情=相(フェーズ)を作る。著者は生活の速度の変化と都市と地方の形成、風景の変化、貧富・家族・病の資本主義的特徴、人々のコミュニケーションの変容から無数の行為が作る相の蠢きを注視する。明治大正の近代を権力の記憶において書かれた歴史でなく、書かれない民衆の行為の伝達過程として捉える試みである本書を読むと、歴史の方がニュートンの線形的時間と平面的空間に乗った近代の学に見える。注釈と解説が懇切丁寧だ。2025/02/21
iwasabi47
2
佐藤健二校注。新全集の成果か?今では使われない意味が判らない語句の解説、当時の事件などの注、他の柳田著作との関連、柳田の文章表現に対する佐藤氏の補足。たぶん精読する為の決定版だと思う。著作自体については、後半にいくほど「世相」の難しいさ展望の厳しさが出て苦しく感ずる。2023/12/24
-
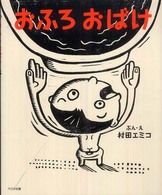
- 和書
- おふろおばけ