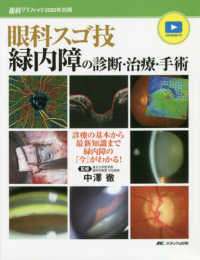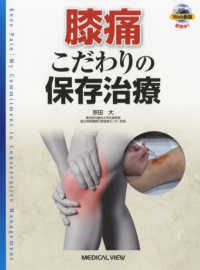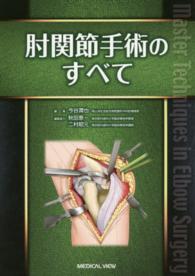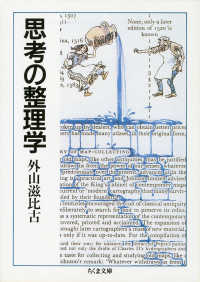出版社内容情報
合戦、自決、処刑による亡骸を埋葬したと伝えられている戦死塚。ときに死者の霊力を崇敬し、ときに怪異や怨霊の源として畏怖する塚伝承には、「敗者」の声なき声を記憶にとどめようとする日本人の心意が刻みこまれている。各地に残る平将門の首塚と胴塚。元寇、戦国の合戦、幕末維新の無数の死者たちの千人塚。敵と味方の死を冷酷に峻別した戊辰戦争──。大幅増補によって全国1686例の戦死塚一覧、現地写真125点を収録した決定版。
内容説明
合戦、自決、処刑による亡骸を埋葬したと伝えられている戦死塚。ときに死者の霊力を崇敬し、ときに怪異や怨霊の源として畏怖する塚伝承には、「敗者」の声なき声を記憶にとどめようとする日本人の心意が刻みこまれている。各地に残る平将門の首塚と胴塚。元寇、戦国の合戦、幕末維新の無数の死者たちの千人塚。敵と味方の死を冷酷に峻別した戊辰戦争―。大幅増補によって全国1686例の戦死塚一覧、現地写真125点を収録した決定版。
目次
序章 「首塚」は、いかに語られてきたか
第1章 「大化の改新」と蘇我入鹿の首塚
第2章 「壬申の乱」をめぐる塚
第3章 平将門の首塚・胴塚
第4章 「一ノ谷の戦い」の敗者と勝者
第5章 楠木正成・新田義貞の結末
第6章 「関ヶ原の戦い」の敗者たち
第7章 「近代」への産みの苦しみ
終章 「客死」という悲劇
補章 彼我の分明―戦死者埋葬譚の「近代」
著者等紹介
室井康成[ムロイコウセイ]
1976年、東京都生まれ。国学院大学文学部文学科卒業、総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程修了。博士(文学)。専攻は民俗学、近現代東アジアの思想と文化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
CTC
てくてく
えびちり
Fumitaka