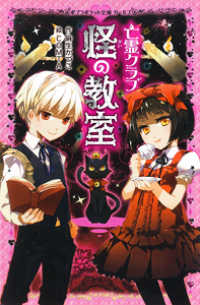内容説明
漢字は日本全国共通と思ったら大間違い!話し言葉に「方言」があるように、漢字にも「地域漢字」や「地域音訓」が存在する。各地の陸や海でとれる多様な産物、祭祀や地元の言葉でさえも訓読みに変えてきた日本人。個性豊かな漢字には、先人からのメッセージが込められている。中国生まれの漢字は、起伏に富んだ日本列島の地形や風土をどのように表現してきたのか、豊富な事例から解説。著者が撮影した看板などの写真も多数掲載。
目次
第1章 漢字と風土―漢字の使用地域とそこに暮らす人々
第2章 北海道・東北の漢字から
第3章 関東の漢字から
第4章 中部の漢字から
第5章 近畿の漢字から
第6章 中国・四国の漢字から
第7章 九州・沖縄の漢字から
第8章 方言漢字のこれから
著者等紹介
笹原宏之[ササハラヒロユキ]
1965年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部で中国文学を専攻、同大学院では日本文学を専攻。博士(文学)。早稲田大学社会科学総合学術院教授。経済産業省の「JIS漢字」、法務省法制審議会の「人名用漢字」、文部科学省文化審議会の「常用漢字」の改正・改定にも携わる。著書に『国字の位相と展開』(三省堂、金田一京助博士記念賞、立命館白川静記念東洋文字文化賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
へくとぱすかる
53
単行本から7年。文庫で再読。漢字の世界がいかに融通無碍でバラエティに富んでいるかを教えてくれる「方言漢字」。県や地方ごとに、特有の文字・字形や読み方がある、と言ってもいいくらいだ。函館では「函」がやや省略した字形で使われる例が多いらしいが、京都でも祇園祭の「函谷鉾」の字は、函館での形と同様か、「凾」だったりする。「岾」は埼玉と京都の不思議な暗合を感じさせるし、「椥」はさらに研究を深められそうだ。方言漢字には、日本でここだけ、という貴重な例が多く、地名と同様、安易に改変したくない文化遺産だと思う。2020/12/26
わ!
6
私にはとても面白いと思える本だった。とにかく全編、難読漢字の大洪水である。「方言漢字」というのは、漢字に関する地域性とでもいうべきもので、そうなると「地名漢字」が多くなるのだが、地名というもの自体が由来の中に地方の歴史や伝説を含んでいるわけだから、やはり方言漢字となるわけだ。著者は「JIS漢字」や「当用漢字」の改正改訂に携わられているそうだが、ここまで念入りにフィードワークをされるかたであれば。「この漢字は、地名のある現地では、まだ盛んに使われている」などの評価ができて、丁寧な改正改訂が成されるだろうな。2023/07/04
takao
4
ふむ2023/02/08
ひじき
4
イントネーションや言い回しの地域差はよく知られていても、漢字の地域差はあまり知られていない。そんな「方言漢字」にスポットライトを当てた本。とにかく情報量が多く、えっ何!?と思っている間に漢字の洪水に押し流されてしまう勢い。第二章以降は各地域の漢字をめぐるエッセイだけど常に漢字を探しておられる。漢字を足で稼いでいる…。地形を表す言葉には同じ音でそれぞれの地域の漢字があったり、同じ字が違う場所でたまたま生まれていたり、各地の工夫がにじみ出るのが面白い。表記揺れも気にしなくていいものがあるというのがいいな。2020/09/18
志村真幸
3
著者は漢字の研究者。JIS漢字、人名用漢字、常用漢字などの整備制定にも関わってきたという。 「方言漢字」とは著者の造語らしいが、その土地でしか通用していない特殊な漢字のことをさす。垈、垳、椣、杁などで、ほかの土地のひとは見たこともないし、当然、読むこともできない。主に地名に使われており、各地から列挙されている数の多さには驚かされた。 そうした漢字の多様性の理由にも、きっちり踏みこんで説明され、漢字の奥深さを思い知らされた一冊であった。 ただ、読み通すのに根気のいる本なのも事実。あまりに羅列的。2021/01/06