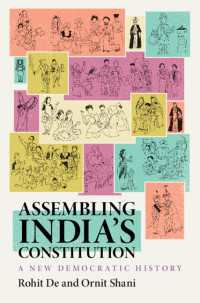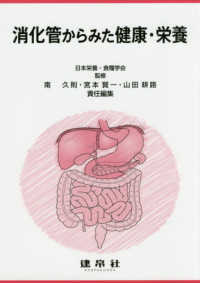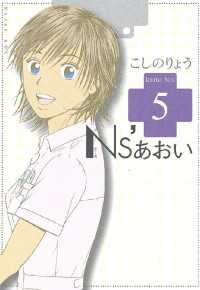- ホーム
- > 和書
- > エンターテイメント
- > サブカルチャー
- > サブカルチャーその他
出版社内容情報
日本の創作文化に欠かせない、キャラクター。17のテーマで大衆文化のコアに挑む。
【執筆参加者】
荒木 浩、前川志織、木場貴俊、金水 敏、芦津かおり、井上章一、永井久美子、佐々木高弘、佐野明子、青木 然、山口記弘、深谷 大、近藤和都、江口久美、松井広志、マイケル・エメリック、久留島元
【目次】
序 〈キャラクター〉と〈世界〉の大衆文化史
第1部 〈キャラクター〉とはなにか
第一章 《キャラクター》と《人格》について
第二章 ヤマト・ハムレット七変化
コラム1 キャラクターと翻訳の可能性
第2部 美人というキャラクター
第三章 美貌の歴史と美術の歴史
第四章 「世界三大美女」言説と戦後日本の美人観――小町とヘレネの交代から考える
第五章 「キャラクター」としての麗子――画家・岸田劉生の《麗子像》連作から
第3部 伝承世界とキャラクター
第六章 「シン・ゴジラ」の世界観――キャラクター化された「荒ぶる神」と神話の世界
第七章 空から獣が落ちてきた――雷獣攷
第八章 タヌキと戦争―日本のアニメ文化における伝承世界の展開
コラム2 是害坊の近世受容――転生する天狗説話
第4部 絵と芸能とキャラクター
第九章 小林清親『百撰百笑』における清国人像
第十章 時代劇ヒーローキャラクターの芸能史
第十一章 歌舞伎とジャニーズ――形を変えて生き続ける文化伝統
第5部 モダンカルチャー・プロジェクション
第十二章 「ヤマト」から「ガンダム」へのメディア史――「記憶すべきもの」と「記憶する人々」
第十三章 グループアイドルの世界観共有と補完――BiS・BiSHを対象として
第十四章 ビデオゲームのキャラクターと世界――「スパロボ」と「サガ」シリーズから考える
内容説明
日本の創作文化、その源泉に迫る。過去のキャラクターと世界観が混合し、未来へと再生産されるメカニズムとは。神話、歌舞伎、アイドル…日本人の美人観の真相、現代の戦隊ヒーローに宿る古典芸能の所作、異国のキャラクターの翻訳可能性など、17のテーマから大衆文化研究のコアに挑み、新たな地平を拓く。
目次
序 “キャラクター”と“世界”の大衆文化史
第1部 “キャラクター”とはなにか(“キャラクター”と“人格”について;ヤマト・ハムレット七変化)
第2部 美人というキャラクター(美貌の歴史と美術の歴史;「世界三大美女」言説と戦後日本の美人観―小町とヘレネの交代から考える ほか)
第3部 伝承世界とキャラクター(「シン・ゴジラ」の世界観―キャラクター化された「荒ぶる神」と神話の世界;空から獣が落ちてきた―雷獣攷 ほか)
第4部 絵と芸能とキャラクター(小林清親『百撰百笑』における清国人像;時代劇ヒーローキャラクターの芸能史 ほか)
第5部 モダンカルチャー・プロジェクション(「ヤマト」から「ガンダム」へのメディア史―「記憶すべきもの」と「記憶する人々」;グループアイドルの世界観共有と補完―BiS・BiSHを対象として ほか)
著者等紹介
荒木浩[アラキヒロシ]
1959年生まれ。国際日本文化研究センター教授。専門は日本古典文学
前川志織[マエカワシオリ]
1976年生まれ。国際日本文化研究センター特任助教。専門は日本近代美術史、デザイン史
木場貴俊[キバタカトシ]
1979年生まれ。京都先端科学大学講師。専門は日本近世文化史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
つーちゃん
かりんとー
近江
ハナさん*