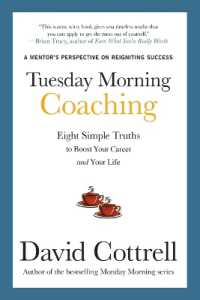出版社内容情報
西田哲学のエッセンスを永井流に丁寧に考察、あらたな付論を加えた文庫新版私の底に汝があり、汝の底に私がある――。「私」と「汝」がともに「彼」に変容することが、言語の成立ということなのだ。西田哲学を他の哲学論と丁寧に比較、論じながら独自の永井哲学を展開。さらに文庫版付論・時計の成立「死ぬことによって生まれる今と生まれることによって死ぬ今」で、マクタガートの「時間の非実在性」の概念を介在させ、考察を深めた。無と有、生と死の本質にせまる圧倒的な哲学書。NHK出版『シリーズ・哲学のエッセンス 西田幾多郎<絶対無>とは何か』に新しく付論を加えて文庫化。
永井 均[ナガイ ヒトシ]
著・文・その他
内容説明
私の底に汝があり、汝の底に私がある―。「私」と「汝」がともに「彼」に変容することが、言語の成立ということなのだ。西田哲学を他の哲学論と丁寧に比較、論じながら独自の永井哲学を展開。さらに文庫版付論「時計の成立」―死ぬことによって生まれる今と生まれることによって死ぬ今―で、マクタガートの「時間の非実在性」の概念を介在させ、考察を深めた。無と有、生と死の本質にせまる圧倒的な哲学書。
目次
第1章 純粋経験―思う、ゆえに、思いあり(長いトンネルを抜けると―主客未分の経験;知即行―真理と意志は合致する;デカルトvs.西田幾多郎)
第2章 場所―“絶対無”はどこにあるのか(言語哲学者としての西田;自覚―「私を知る」とはどういうことか;場所としての私 ほか)
第3章 私と汝―私は殺されることによって生まれる(思想の体系化;田辺元の西田批判;存在する私への死)
著者等紹介
永井均[ナガイヒトシ]
1951年生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得。日本大学教授。専攻は、哲学、倫理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
へくとぱすかる
ころこ
ころこ
ころこ
-

- 和書
- 少女探偵月原美音