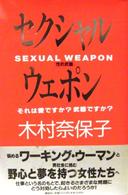出版社内容情報
古代の詩歌のひびきを蘇らせた、奇蹟の歌人。全歌集を収める初の文庫版!折口信夫(釈迢空)は近代日本にまるで奇蹟のように、古代の心、古代の詩歌のひびきを、鮮烈に蘇らせた歌人であった――。
短歌滅亡論を唱えるも、その真意は再生への願いであり、日本語の多彩な表記を駆使しながらつねに短歌の未来と格闘し続けた。
折口が残した6冊の歌集に私家版・自筆選集、短歌拾遺、
さらに関東大震災に直面し、短歌形式に収めることのできない苛烈な体験を詠んだ詩作品含めた、初の文庫全歌集。
「葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり」
生涯「旅びと」であった折口の姿が立ち現れてくる。
海やまのあひだ
春のことぶれ
水の上
遠やまひこ
天地に宣る
倭をぐな
私家版・自筆選集
短歌拾遺
詩拾遺
解題
解説 岡野弘彦
略年譜
作品初句索引
折口 信夫[オリクチ シノブ]
1887?1953。国文学者、民俗学者、歌人、詩人。大阪生れ。釈迢空は歌人としての名。天王寺中学卒業後、国学院大学に進み、国学者三矢重松から深い恩顧を受ける。1919年国学院大学講師となり、のち教授として終生国学院の教職にあった。、正岡子規の「根岸短歌会」、後「アララギ」に「釈迢空」の名で参加し、作歌や選歌をしたが、やがて自己の作風と乖離し、アララギを退会。1924年(大正13年)北原白秋と同門の古泉千樫らと共に反アララギ派を結成して『日光』を創刊した。
岡野 弘彦[オカノ ヒロヒコ]
歌人。1924(大正13)年、三重県生まれ。國學院大學卒業。在学時から折口信夫(釈迢空)に学び、没年まで師事する。 処女歌集「冬の家族」で現代歌人協会賞を受賞。主な歌集に『滄浪歌』(迢空賞受賞)、『海のまほろば』(芸術選奨文部大臣賞)、『天の鶴群』(読売文学賞)、『折口信夫伝』(和辻哲郎賞受賞)など。1995年?2007年に宮年宮内庁御用掛をつとめる。1988年、紫綬褒章受章。日本芸術院会員、文化功労者、國學院大學名誉教授。
内容説明
折口信夫(釈迢空)は近代日本に奇蹟のように、古代の心、古代の詩歌のひびきを、鮮烈に蘇らせた歌人であった。短歌滅亡論を唱えるも、心は再生を願い、日本語の多彩な表現を駆使しながら、短歌の未来と格闘し続けた。『海やまのあひだ』から『倭をぐな』までの全歌集に私家版・自筆歌集、拾遺、さらに関東大震災の苛烈な体験を詠んだ詩作品をも収める決定版。
目次
海やまのあひだ
春のことぶれ
水の上
遠やまひこ
天地に宣る
倭をぐな
私家版・自筆歌集
短歌拾遺
詩拾遺
著者等紹介
折口信夫[オリクチシノブ]
1887(明治20)年~1953(昭和28)年。国文学者、民俗学者、歌人、詩人。大阪府生まれ。「釈迢空」は歌人としての名。天王寺中学卒業後、國學院大學に進み、国学者三矢重松から深い恩顧を受ける。1919年に國學院大學講師をつとめた後、教授に。また1923年に慶應義塾大学講師となり、終生教授をつとめた。正岡子規没後、門人らによる「アララギ」に参加。退会後、1924年に北原白秋と同門の古泉千樫らと反アララギ派を結成。「日光」創刊に参加し、1927年の終刊以後は結社に関わらず、日本の詩である短歌の再生に努めた
岡野弘彦[オカノヒロヒコ]
1924(大正13)年、三重県生まれ。歌人。國學院大學在学時から折口信夫に学び、没年まで師事する。処女歌集「冬の家族」で現代歌人協会賞を受賞。主な歌集に『滄浪歌』(迢空賞受賞)、『海のまほろば』(芸術選奨文部大臣賞)、『天の鶴群』(読売文学賞)、『折口信夫伝』(和辻哲郎賞受賞)など。1995年~2007年、宮年宮内庁御用掛。1988年、紫綬褒章受章。日本芸術院会員、文化功労者、國學院大學名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
松本直哉
roughfractus02
内藤銀ねず
belle
-

- 電子書籍
- お見合い婚にも初夜は必要ですか? 新装…
-
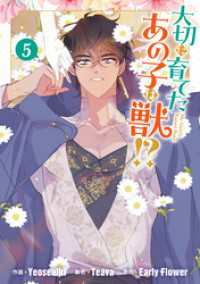
- 電子書籍
- 大切に育てたあの子は獣!?: 5 カラ…