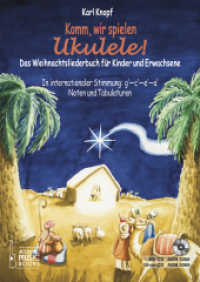内容説明
江戸時代、新宿は甲州街道の宿場にすぎず、銀座は下町の代表であった。維新当時でも、蔵前には吉原通いの駕籠を狙う追剥が出没していた。しかし、江戸でも東京でも変わらない場所がある。寄席である。古典落語の名作の舞台を歩く、春夏秋冬、それぞれの季節に適した20コース。「目黒のさんま」「四谷怪談」など、代表的な演目のあらすじも収録。更に江戸時代の寄席も特定した便利なイラストマップもついた、落語散歩の決定版。
目次
春(湯島・本郷「片足ァ本郷へ行くわいな」;千住・王子「人間には気をおつけ、馬の糞かもしれない」;麹町「麹町にね、サルお邸の旦那様があったんだよ」;上野「清水の観音さまィ、一生懸命信心してごらん」;向島「お花見で女の子が騒いでるはまことに風情のあるもので」)
夏(亀戸「祈る神様仏様、妙見さまへ精進の」;両国「川開きの当日、両国橋は一杯の人出です。通りかかったたがやさん」;浜町「長谷川町の三光新道に常盤津歌女文字という」;深川「深川八幡の祭りがたいそうよくできたという評判で」;四谷・新宿「はて恐ろしい、執念じゃなァ」)
秋(蔵前・神田「もうすんだか」;目黒「さんまは目黒にかぎる」;京橋・銀座「お奉行さまという強い味方が付いていらァ」;日暮里・根津「ざっと拝んでおせんの茶屋へ」;谷中・根岸「また茶の湯か」)
冬(牛込「目がうしろにありゃあウシロメの神楽坂だ」;品川・鈴ケ森「心中の相手は金ちゃんに決めよう」;芝・高輪「酒はよそう、また夢になるといけねえ」;浅草「十八間四方のお堂に安置したてまつる聖くわんぜおん菩薩」;麻布「麻布絶江釜無村の木蓮寺に着いたときにはくたびれた」)
著者等紹介
吉田章一[ヨシダショウイチ]
1933年、岡山市生まれ。落語研究家。66年東京大学工学部を卒業。造船会社に勤めながら、落語の研究や町歩きを続ける。2002年から07年まで、帝京平成大学で落語や江戸風俗の講師を務めた他、早稲田大学エクステンションセンターなどで落語の講座を担当している。東大落語会、諸芸懇話会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
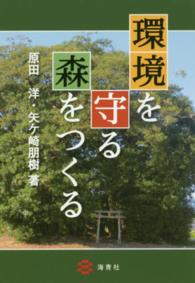
- 和書
- 環境を守る森をつくる