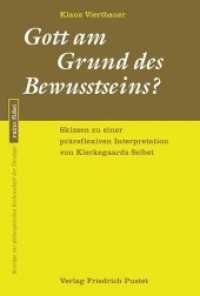内容説明
二〇〇一年十二月、米エネルギー企業大手エンロンが破綻した。一介の地方ガス会社は、いかにして世界にエネルギー革命をもたらし、なぜ突如破綻したか?同社と米国政府、ウォール街、会計事務所との癒着とは、いかなるものだったのか?エンロンが駆使した金融工学と会計操作のからくりに徹底的にメスを入れるとともに、貧困家庭から這い上がろうとして戦い、破滅した幹部たちの人間ドラマに光を当てるドキュメント経済小説。
著者等紹介
黒木亮[クロキリョウ]
1957年、北海道生まれ。カイロ・アメリカン大学大学院(中東研究科)修士。都市銀行、証券会社、総合商社英国現法プロジェクト金融部長を経て、作家。著書に国際協調融資を描いた『トップ・レフト』、アジア通貨危機を描いた『アジアの隼』など。国際金融の舞台で活躍した経験を活かした新しい経済小説の書き手として注目を集めている。ロンドン在住
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まつうら
23
SOX法のきっかけとなったエンロン事件を扱った作品。もともとはガスの供給会社だったのが、巨大なエネルギー企業となった背景は、会計事務所を巻き込んだ不正会計に過ぎない。循環取引とかSPEとか出てくるが、バランスシートをよく見せるためのテクニックであり、ビジネスの実体は何もない。滅びるべくして滅びたというのが印象だ。 ただ、「天候デリバティブ」だけはおもしろいと思った。雨が降り過ぎては困る事業がある一方、農業のように雨が降らないと困る事業とがあって、金融商品でこれらを繋ぐというアイデアにはとても感心した。
なお
18
エネルギービジネスで頭角をあらわしたヒューストンの会社、エンロン。元々は地方の電力送電会社であり、電力自由化で画期的な商品を生み出し、また金融工学を駆使して複雑な会計方法を使用して負債を隠していた。 アンダーセンの解散をメインで読みたかったのだが、この作品はエンロンの繁栄から衰退までがメイン。 社内の恐怖政治がこの結果をもたらしたということがよくわかった。2025/04/13
nekozuki
18
巨大エネルギー企業エンロンがなぜ破綻することになったのか、内部の組織腐敗と複雑な会計トリックを小説として詳しく説明している。今となってはここまでのオフバランス取引は認められないが、それも本件が発端といっても過言ではないと思う。また、天候デリバティブなど画期的な商品を生み出した点で当社がイノベーティブであったことに疑問の余地はないが、そのリスクを当社のみで負うことで利益追求したことに最終的な破綻に向かう原因があったように思う。2019/05/06
DEE
17
アメリカの巨大エネルギー会社エンロンが、破竹の勢いで世界を席巻し、その後多額の負債を抱えたまま消滅するまでのお話。 他社を力でねじ伏せ、身内の中で資金を回して多額の利益を出しているように見せていたエンロンと、その数字を信じ切っていた投資家たち。 ほんの僅かな綻びで一気に崩れてしまう怖さを、全く無関係な対岸から眺める面白さ。 ちょっと話は古いんだけど、金融に疎くても楽しめる一冊。2020/05/15
ヤギ郎
12
世界規模の金融危機をもたらした米国エネルギー企業・エンロンの盛衰を描いたドキュメント経済小説。膨大な量の参考文献をもとに、史実に基づいて書かれていることがほとんど。物語のような事件らしい事件が起こることなく、社員は金融工学と会計操作を用いて、エンロンに莫大な利益をもたらした。想像を越えるキャッシュのやり取り、全貌を掴むことのできない複雑なシステム、これらに飲まれたエンロンは少しずつ破綻へと進む。電気や天候といった、利益になりにくいものを金融商品としたところはエンロンの成果をいえるだろう。2021/03/21
-
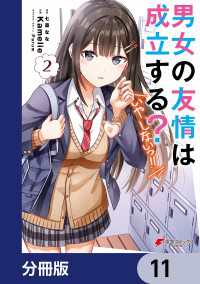
- 電子書籍
- 男女の友情は成立する?(いや、しないっ…
-
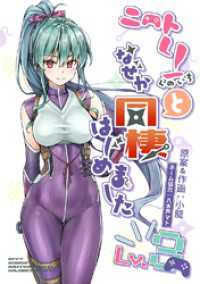
- 電子書籍
- ニートくノ一となぜか同棲はじめました【…