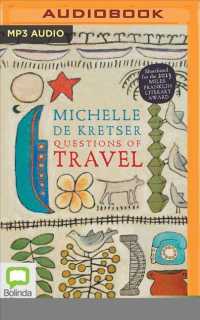出版社内容情報
うち続く天災と、源平争乱という大きな渦の中で生まれた無常の文学。平安末期、大火・飢饉・大地震、源平争乱や一族の権力争いを体験した鴨長明が、この世の無常と身の処し方を綴る。人生を前向きに生きるヒントがつまった名随筆を、コラムや図版とともに全文掲載。
鴨 長明[カモノ チョウメイ]
著・文・その他
武田 友宏[タケダ トモヒロ]
編集
内容説明
『方丈記』が書かれたのは、まさに源平の戦いの頃、武家の社会へと価値観が大きく変わり、天変地異が次々起こる不安な時代であった。著者の鴨長明は、葵祭で有名な下鴨神社の将来を約束された神官の子として生まれた。だが、ついにその座に就くことなく山里の小さな庵に隠棲し、混迷する都のさまを見つめつつ、この世の無常と身の処し方とを綴った。現代の我々にとって、スローライフを提唱する示唆に富んだ随筆でもある。
目次
万物をつらぬく無常の真理
無常をさとす天災・人災
無常の世に生きる人々
過去の人生を顧みる
山中の独り住まい
わが人生の生き方
跋
著者等紹介
武田友宏[タケダトモヒロ]
1943年、青森県生まれ。國學院大學文学部日本文学科非常勤講師。國學院大學大学院文学研究科博士課程修了。日本文学専攻。編著に『有職故実日本の古典』等角川書店の多くの国語・古語辞典の編纂に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
147
巻末の解説ではなく各章の解説が読みたくて購入した本書。期待以上で奮っていました。いいじゃないかいいじゃないか方丈記!2022/04/09
月讀命
101
古典は素晴らしい。ただ、高校時代に古文の授業を真剣に学習してこなかった私にとってはハードルが高い。 しかし、このビギナーズクラシックは、現代文と古文の両方で解説して下さるので 親しみやすく理解し易い。鴨長明は、方丈記の中で、特に災害について多く書き綴っている。地震、津波、竜巻、火事、飢饉等を事詳細に記述しており、その光景を端的に描写しながら、世の中の無常観を物語っている。今般、未曾有の被害を齎せた東日本大震災が発生し、日本中大打撃を受けたが、惨劇は今も昔も同様であると感じ、何時の時代にも無常観を見い出す。2012/04/10
ちゃちゃ
74
京都日野山で隠棲する孤独な鴨長明の姿がここにはあった。「行く河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」あまりにも有名な美しい冒頭の一文。そこに見事に具現化された仏教的な無常観。平安末期に都を襲った大火、辻風(竜巻)、飢饉、大地震といった天災に加え、平清盛によって強行された福原遷都による人災。克明な記録文学のような印象に引きずられて見えなかった長明の孤独。悲運な生涯の果てに到達した、自由気ままで身の丈に合った侘び住まいへの満足と矜恃。人間味溢れる長明。今回初めて通読することで、新たな発見に心が躍った。2017/10/14
Gotoran
71
『徒然草』に続き、古の日本三大随筆、第二作品の『方丈記』も角川ビギナーズクラシックスで。現代語訳、読み下し、解説という構成で、読み易く、解説では時代背景や用語の説明もあり、さらにその章の意味合い、随所にある挿絵が理解の手助けになる。琴や琵琶を愛した長明ならではの流麗な文章で、世俗の成功からの挫折体験、平安末期の地震、竜巻、火事などの災害の続発から、人生の無常観について、思いを巡らせている。次は、最後の『枕草子』を読むことにしたい。2017/08/31
れみ
70
鎌倉時代の初め頃に書かれた随筆。冒頭の部分くらいしか知らなかったけど文章が原文でもわりと分かり易かった。あと一昨年の大河ドラマ「平清盛」にハマってたので知ってる名前や出来事が登場してるのが、お!って感じで面白かった。それから、解説にあった「徒然草」との比較が興味深かったので次に挑戦する古典は「徒然草」にしようかな。このシリーズ、何作か読んでるけどなぜかみんな解説が毒舌だったり辛辣だったりしてびっくりする(^_^;)2014/06/06