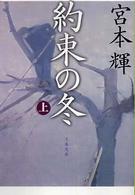内容説明
十七年間の教師生活を通じて知った子どもたちのやさしさ、個性の豊かさ。児童雑誌「きりん」に掲載された、底抜けに明るくユニークな子どもの詩の数々。どんな時も、子どもたちが自分を支え、育んでくれた―。「兎の眼」「太陽の子」「天の瞳」の著者・灰谷健次郎が綴る、子どもの可能性の大きさ、そして人間への熱い思い。限りない感動に満ちた、灰谷文学の原点。
目次
『ぼくは悪いことをした』というぼくの聖書
「きりん」の幼い戦士たち
二つの盗み
別離の向こうから
骨くんの話
優しさと反抗と
希望への道
沖縄の空
肝苦りさ
優しさの源流
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちえ
35
思い出した。学生時代所属していたサークルは教育や保育を専攻している人が多く皆で灰谷健次郎さんの本を随分読んだ。その時読んだのは新潮文庫だったはず。だからウン十年ぶり、ほぼ忘れていて再読。そしてどのページもどのページも心にずしんと来る。読み終えてもなかなか感想が書けなかった。灰谷さんのお兄さんへの悔悛や自身への厳しい目、沖縄へのまなざし。読んでいて、人間が生きていく中で無駄なこと、意味のないことは何もないと思う。灰谷さんの本はいつまでも読み継がれてほしい。2023/04/01
あや
13
児童文学者で元小学校教諭の灰谷健次郎さんの自伝的珠玉のエッセイ。貧しい時代を経て小学校教諭になる。元従軍慰安婦との出会い。看護婦と騙されて戦争に行ったら慰安婦にされて気がふれてしまったという女性の存在をこの書物によって知った。従軍慰安婦についてのアートの展示の是非や日本の謝罪の在り方の議論があるけど私はそのたびにこの本の気のふれてしまった騙された元慰安婦の方の存在を思い出す。謝るとか謝らない以前にそういう方が実在するという厳然とした事実から目を背けては前にすすむことはできない。2020/03/15
マネコ
11
児童文学作家という情報だけで読み始めた本書ですが、出だしから荒んだ時代のよどみを生きた著者の半生が語られ軽い気持ちで読めなくなりました。著者も取り上げられている子どもの作文も飾らない文章ながら原液を飲まされるような重さがあります。人の光も闇も分け隔てなく書かれているので、非常に引き込まれました。灰谷作品を読みたくなる一冊です。2019/01/30
あい
11
新聞のコラムで「子どもに関わる大人の必読本の一つ」として紹介された一書。本当の優しさとは何か、深く考えさせられた。世間では厳しさも優しさのうち、みたいな風潮がある。そういう優しさも時としてある。だが、ここで描かれる優しさは、遥かにに大きく暖かく柔軟で、そして深い。著者は言う。「優しさというものは情緒の世界にあるものではなく、自らを変え、他人をも変える力として存在している」と。その優しさは特別なものではなく人間の本性として備わっているものなのだと、本書に登場する子どもたちはその純粋さをもって教えてくれる。2013/11/08
大泉宗一郎
10
『この本を読んで、人の悲しみを自分の悲しみとし、人の喜びを自らの喜びに変えることのできる優しい人になろうという目標を立てた。次にこれを読んだ時、自分の中に何人の人間がいるのか、勘定して、振り返って下さい』ちょうど、人間性の向上に一番前向きな姿勢を見せていた時期の、自分の言葉。この本を読んで、どうしようもない感動を覚え、学習ノートに感情をぶちまけた時の言葉。いま見返すと、こそばゆくもあり、頼もしくもある。だけど、同時に恥ずかしくもある。それは、たぶん今の自分に対する羞恥だと思う。しっかりしなきゃな。2015/01/29
-

- 電子書籍
- 【電子限定版】転生しまして、現在は侍女…
-
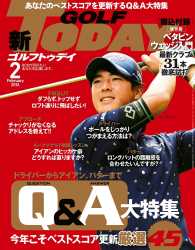
- 電子書籍
- GOLF TODAY 2016年2月号…