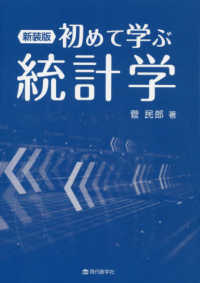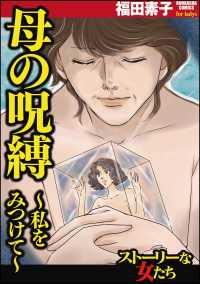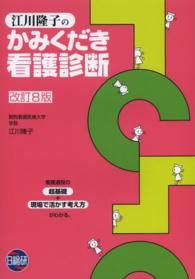内容説明
天才詩人アルチュール・ランボーは、母音に色を感じたという。抑えられない笑いと涙を繰り返す患者や、自分の左側を完全に無視する患者。この興味深い現象は、すべて脳が演出している。切断された手足がまだあると感じる幻肢患者の鏡を使った治療で世界を驚愕させた著者が、ロングセラー『脳のなかの幽霊』に続いて、まだまだ広がる未知の領域に深くわけいり、さらなる知的冒険へと誘う第2弾。
目次
第1章 脳のなかの幽霊
第2章 信じることは見ること
第3章 アートフルな脳
第4章 紫色の数字、鋭いチーズ
第5章 神経科学―新たな哲学
著者等紹介
ラマチャンドラン,V.S.[ラマチャンドラン,V.S.][Ramachandran,Vilayanur S.]
カリフォルニア大学サンディエコ校の脳認知センター教授、所長、同大学心理学部神経科学科教授
山下篤子[ヤマシタアツコ]
1952年生まれ。北海道大学歯学部卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
44
<心の科学>は、物理学=宇宙論の目覚ましい進歩(多宇宙)、生物学や進化論の革命(ゲノム)に比べると、沈滞していた。しかし1990年代から青銅器時代に入り目覚ましい進展を遂げていると、著者はいう。本書は、1998年に脳科学が明らかにした常識を覆す事実を一般読者に示し衝撃を与えた「脳の中の幽霊」の自著解説本のようなもの(講演集で原著2003)。その意味で、新味性には乏しいが、脳科学が解明しつつある「芸術性とは何か」や「意識や自由意思とは何か」という科学が対象としてこなかったテーマに直接答えるもので興味深い。2014/10/30
zirou1984
36
原題「The Emerging Mind」。過去半世紀に渡ってイギリスの知的・文化的象徴であり、名立たる学者がその壇上で話すことになったリース講演を始めとしたいくつかの講演をまとめたもの。日本語のタイトルが示している様に多くが前著と重複しているのだが、本作では講演の内容を基にしてるだけあって種々の事例がより簡潔に示されている。それ以外にも脳とアートの関係について推測交じりながらより掘り下げられており、芸術や宗教的能力が脳の一部のモジュール部位に依存しているという話は興味深い。僕らの人格だって同じなんだよ。2014/07/31
ヨクト
25
人気を博した前著「脳の中の幽霊」の講演を基に書籍化したもの。そのため前著と重複する部分が多々あるが、言語についての考察や数字の色の話はさらに深く進められており面白い。脳の中は、1番身近で、1番未知で、1番面白い分野かもしれない。そう思わせてくれるラマチャンドラン博士である。2015/01/12
猫丸
15
前著と同様、脳損傷に付随する異常を契機にノーマルとされる人類の脳機能を追求していく。複合的・重層的な構造の一部に綻びを発見し、そこに脳の局所的単一モジュールの存在を仮定し、二分法で推論を進めていく。「AならばB」がただちに「BならばA」を意味しないのは論理の初歩であるが、二分法に落とし込めればそこを突破できる。「1組の生徒は白帽、2組の生徒は赤帽」が担保された状況では「赤帽すなわち2組」で正しいのだ。それを要素還元主義と批判するのはお門違いで、強靭な論理に安易に形而上的思考を対置するのは「逃げ」である。2021/02/03
紫羊
15
「脳のなかの幽霊」の続編だと思って読みだしたが、そうではなくて、簡潔にまとめたものだった。でも、これはこれで面白く読めたし、頭の中で整理ができて良かった。2013/10/13