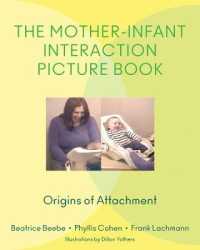内容説明
六月のロンドン。心地よい空気が満ち溢れたセント・ジェームズ公園を、ダロウェイ夫人が歩いている。五十の坂をこして、自分がとても若いような気もするし、お話にならないほど老けたような気もする―。人間のたゆたうような意識の流れを、心に雨のようにそそぎこむ独特の文体と、新鮮な構図でまとめあげ、さまざまな人生を謳いあげる。新手法をはじめて自由に使いこなし、見事な成功をおさめた、記念すべきウルフの最高傑作。
著者等紹介
ウルフ,ヴァージニア[ウルフ,ヴァージニア][Woolf,Virginia]
1882‐1941。ロンドン生まれ。膨大な蔵書に囲まれた知的環境で成長し、後にブルームズベリー・グループと呼ばれる思想グループの中心的人物として創作に励んだ。13歳の頃からあらわれていた精神の病の兆候は消えることなく、59歳のときに入水し自らの命を絶つ
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
300
『失われた時を求めて』が頭をよぎる。プルーストとウルフには、同時代を生きたということ以上の相通性がありそうだ。ここでの物語の表層的な意味での舞台はロンドンのウエストミンスター。時はダロウェイ夫人の邸でパーティが開かれる日の朝から夜のパーティまでのわずか半日。しかし、クラリッサによって、そしてまたピーターによって、しばしば30数年前のブアトンが回想される。それは彼らにとっての、その後の大きな分岐点だったのだ。一方、本質が細部にこそ宿るのだとすれば、クラリッサが本当に求めていたのはサリーとの愛ではなかったか。2015/09/11
どんぐり
94
1955年刊行の角川文庫を定本にした富田彬訳によるウルフの代表作。「人間のたゆたうような意識の流れを、心に雨のようにそそぎこむ独特の文体」とあるものの、残念ながら和訳があまりにも古くさく、また意味不明な箇所がいくつもあって、私の心には一向に届いてくれない。ウルフ本は複数翻訳が出ているので、やはり新訳を読むべきだったと後悔する。訳文意味不明の例;「議事堂の自鐘のあとから、こまごましたことをスカートの膝にいっぱいいれて、遅ればせにはいってきたその時計の音は、ペチャクチャと、ざわめく波のようにひびいた。→2022/01/08
Willie the Wildcat
50
再会。変化と不変、それぞれへの期待と恐れ。過去の思い出が、目の前の現在と交錯。一日という時間軸で、時代背景を踏まえた心の表裏を描写。クラリッサとセプティマスの暗喩的対照が象徴。前者が意識的に、後者が無意識の中で登場人物の心を重ねる。”全う”へのYardstick。一方、「思い」へ至る過程の理想と現実のGAPへの苦悩。クラリッサが評価軸。解釈の積み重ねの生んだ擦れ違い。憎悪を踏まえても、パーティ会場に来るキルマンが印象的。良くも悪くも、時代の象徴への向き合い方を通した人生の振り返りかな。2015/10/22
ちえ
43
主催するパーティの日の朝、花を買いに行くダロウェイ夫人。その1日が変わっていく登場人物の意識の流れで構成。ダロウェイ夫人と昔の恋人ピーター・ウォルシェ、第一次大戦の帰還兵セプティマスとイタリア人の妻ルクレチア。直接出会うことはないが小説の中で密接に繋がっている。後書きによるとセプティマスはダロウェイ夫人の分身という位置づけらしい、と書いていても難解で正直後書きがなければ何のことやら私にはとても理解できなかっただろう。何度も挫折したこの本を読了出来たことで良しとしよう😅◆ガーディアン必読選書10002024/01/14
miyu
40
多くの人物のとりとめもない考えが次々と入れ替わる。だからよく言われるウルフの手法を意識しながら読むと逆に難しくなる。人々の心の移ろいに普通に耳を傾ければいいだけなのに。そこが彼女の面白さだ。誰もがクラリッサ・ダロウェイと何らかの関わりがあり彼らの心を垣間見ることで朧げだった彼女の輪郭もくっきりと浮かぶ。そして何人かの人物はクラリッサの別の人格だ。特にセプティマスはウルフも断言しているようにもう一人のクラリッサ。実は危うく今にも消え入りそうな心持ちの一人の女のたった一日の複雑な心の軌跡。とても愛おしかった。2017/12/16