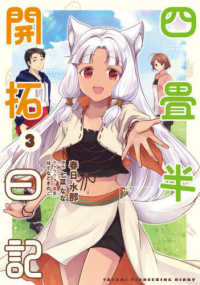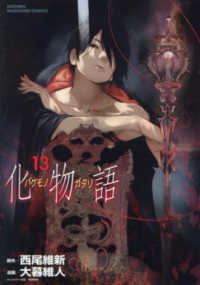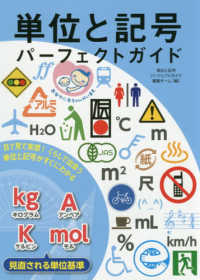出版社内容情報
本土防衛の天王山となったマリアナ沖海戦。乾坤一擲、必勝の信念で米機動部隊に殺到した日本軍機は、つぎつぎに撃墜される。電子兵器、兵器思想、そして文化――。勝敗を分けた「日米の差」を明らかにする。
NHK取材班[エヌエイチケーシュザイハン]
編集
内容説明
太平洋戦争域で守勢に回った日本は、絶対国防圏を設定し新たな戦争指導方針を決定した。一方、アメリカもB29による日本本土爆撃を決定し、サイパンは前線基地として不可欠となった。天王山となったマリアナ沖海戦。乾坤一擲、必勝の信念で米機動部隊に殺到する日本軍機は、目前でつぎつぎに撃墜される。勝敗を分けたのは、新兵器のレーダーとVT信管。電子兵器の差であり、兵器思想の差であり、文化の違いであった。
目次
1 サイパンを死守せよ
2 日本のレーダー
3 日米の兵器思想
4 戦いを制したエレクトロニクス技術
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェルナーの日記
98
太平洋戦争における日米両陣営の兵器開発という視点から描かれた1冊。日本は攻撃力を重視し、先手必勝・一撃必殺という兵器を開発。ゼロ戦は、その典型的な設計思想を基に旋回能力等の向上させるため極端といえるほど軽量化を進めた。その結果、大戦初期において大きな戦力となった。逆に米国のヘルキャットは、防御力を重視して装甲を厚くし、空母に大量に搭載できるように翼を折りたためるようにする。大戦初期においては、重量の大きさからゼロ戦と比べ、その性能差は著しく劣っていた。しかし、その後エンジンの強化等を果たし立場が逆転する。2016/04/11
CTC
12
第3弾はレーダーやVT信管といった科学兵器開発を通して用兵思想の違いを描く。米のVT信管を用いた砲弾は、“真珠湾”を受けて、42年3月開発着手、翌1月には順次改良されつつ実戦投入。「レーダーと原子爆弾に匹敵する」重要度とされたそうだが…凄まじい開発力だ。一方の旧軍では“防御”のための開発は顧みられなかった。米機は被弾しても簡単には堕ちない。万一の際はパラシュートに加え救命キットがあった。決死の旧軍パイロットより、“護られた”米軍パイロットのほうが、ときに勇敢になれたのでは?という指摘は恐らく正しい。2016/07/04
Shin
8
『永遠の0』を読み、久々に旧日本軍の「負けるべくして負ける」体質に暗澹たる気分になり、積読本のままになっていた本書を手に取った。零戦を始め、大戦後期に日本の熟練搭乗者たちがことごとく犠牲となったVT信管やレーダー。日本でも個々の技術は萌芽していたが、古い戦術思想や組織の壁によってそれらが活かされることはなく、結局、科学技術の運用力不足は最前線での理不尽な人的犠牲で贖うこととなった。本書を読み、『永遠の0』の内容を思い出すと、改めて胸が締め付けられるような心持ちがする。 2013/04/29
Hiroshi
5
1992年に放送のNスペ「ドキュメント太平洋戦争」を書籍化したもの。第3巻は「エレクトロニクスが戦いを制す」。日本と米国の科学技術力、特にエレクトロニクスに焦点を絞り、その科学技術力の差がどのような局面で顕著に現れたかを検証する。その舞台は昭和19年6月のマリアナ沖海戦だ。両国のエレクトロニクスの差が明確に反映したレーダー、日本の主力戦闘機零戦と米国のF6F戦闘機に見られる航空戦力の差、全面的に米軍に配備されたVT信管の威力が、この戦いの明暗を分けたからだ。◆米軍はサイパン島攻略を開始。絶対国防圏を守る。2021/07/09
サンフランちんすこう
3
「攻撃は最大の防御なり」という日本軍の思想によってレーダーの開発は進まず、ゼロ戦の防御・防弾の改善に取り組まなかった。結果、多くの戦死者が出ることになった。全ては合理的思考を持たない上層部のせいである。 パイロットを失うことは自軍の大きな損失と考えた米軍と攻撃に全振りしてパイロットを消耗品と考えた人命軽視の日本軍。無意味な精神論を掲げ、トラブルがあっても現場の各個人がなんとかしろという体制は現在の日本に蔓延るブラック企業に色濃く残っている。2020/10/12