内容説明
鉄道でどこかに行くことだけではなく、鉄道に乗ることそのもののたのしさが分かる1冊。東海道、関東、近畿、九州、東北など、その土地ごとの路線の乗りこなし方と、逃したくない見どころ、地方線ならではの味わいなどを紹介。また、時刻表の読み方や、路線の歴史、ちょっとした雑学などをひもときながら、これからはじめて鉄道旅行をたのしみたいという人にも分かりやすく、その魅力と奥深さを伝えます。
目次
鉄道旅行のたのしみ(東海道の巻;関東の巻;近畿の巻;山陽・四国の巻;九州の巻;北陸・山陰の巻;中央・上信越の巻;東北の巻;奥羽・羽越の巻;北海道の巻;東日本私鉄の巻;西日本私鉄の巻)
駅は見ている(名古屋駅;新宿駅;天王寺駅;高松駅;直方駅;米子駅;塩尻駅;青森駅;新庄駅;岩見沢駅)
著者等紹介
宮脇俊三[ミヤワキシュンゾウ]
1926年、埼玉県川越市に生まれる。51年、東京大学文学部西洋史学科卒業。出版社勤務を経て、鉄道紀行を中心とする執筆活動に入る。著書は、『時刻表2万キロ』(第5回日本ノンフィクション賞)、『時刻表昭和史』(第6回交通図書賞)、『殺意の風景』(第13回泉鏡花文学賞)、『韓国・サハリン鉄道紀行』(第1回JTB紀行文学大賞)ほか多数。99年、第47回菊池寛賞を受賞。2003年2月、逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みやけん
31
★★★★☆当時はまだ大社駅も現役。名鉄の新名古屋駅の発着・塩尻駅もっと見ておけば良かったな。今度直方駅に当時の痕跡を探しに行こう。台湾に日本の新幹線が走るとは予想もしなかっただろうなぁ。2017/11/30
ゐづる
17
日本各地の鉄道の見どころを、宮脇俊三さんの名文でたどる本。30年ほど前の話なので、多少廃止路線や新線切替などありますが、基本は変わっていません。個人的にはスイッチバックとループが好きなんですが、和歌山線のスイッチバックなど、全然知りませんでした。最近まで残っていたので乗ればよかった・・・とはいえ、まだまだそういう場所はあるから、残ってるうちに急いで乗りたいとおもいます。2014/01/18
浅香山三郎
16
1986年の集英社文庫の再文庫化。新潮文庫のシリーズに入つてなかつたから、今迄読んでなかつたのかも。前半の「鉄道旅行のたのしみ」では、国鉄時代の各線の魅力をやや駆け足で語り、後半「駅は見ている」は名古屋、新宿、天王寺、高松等の大きな駅のほか、米子、塩尻、青森等の地方の駅の表情を描く。後半が断然味はい深く、とくに天王寺駅が面白かつた。1983年頃の阪和線ホームの延長や、今はなき天王寺うどんの活気、駅のホームレス対策についてなど、昔の天王寺駅の雰囲気がよく伝わつてくる。2019/04/15
saga
15
鉄道旅行を“路線”と“駅”の視点から書いた一風変わった紀行文。路線では、いつもの著者であれば出発駅から到着駅までの列車時刻を克明に記すのに反して、大きく紹介する地方の路線名を辿る手法を採っている。路線間の接続の良し悪しを論ずるのではなく、その地方の地史・歴史に目がいくような紀行も有りなのだと思わせてくれる。一つの駅だけを取材した紀行文は珍しいと思う。その駅の始発から最終までを見ながら、様々な人間模様、歴史などを綴る文章に、あらためて感心させられた。2013/06/23
marsan
7
図書館本。久しぶりに宮脇俊三さんを読みたくなって。若い頃、「時刻表2万キロ」「最長片道切符の旅」を読んで旅情をかきたてられ、ワクワクした記憶がある。さて、本書からは国鉄民営化前の様子がうかがえて懐かしかったが、特に「天王寺駅」のところは、かつて通勤で毎日利用していたので『天王寺うどん』や『ホームレス』は身近だったし、阪和線が今のように大阪環状線に乗り入れていなかったので、紀勢方面の匂いに溢れていたプラットフォームに佇むと旅に出かけたくなったものです。24542024/11/11
-
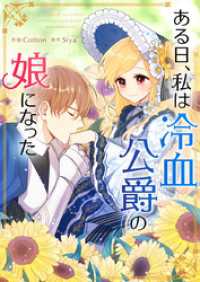
- 電子書籍
- ある日、私は冷血公爵の娘になった【タテ…








