内容説明
1960年代の新宿―。吃音と赤面対人恐怖症に悩む“バリカン”こと建二と、少年院に入り早すぎた人生の挫折を味わった新次は、それぞれの思いを胸に、裏通りのさびれたボクシング・ジムで運命の出会いを果たす。もがきながらもボクサーとしての道を進んでいく2人と、彼らを取り巻くわけありな人々の人間模様。寺山修司唯一の、珠玉の長編小説。
著者等紹介
寺山修司[テラヤマシュウジ]
1935年、青森県生まれ。早稲田大学中退。67年、演劇実験室「天井桟敷」を設立。演劇・映画・短歌・詩・評論など意欲的に活動。83年、敗血症により逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
148
寺山の初めての長編小説(そして同時に唯一の?)ということなのだが、色々な意味で寺山らしさの横溢する作品だ。彼はこれを「モダンジャズの手法」によって書いたと述べているが、そもそも登場人物の役柄を措定して、それらの人物を動かしていくというのは寺山が親しんだ演劇の手法でもあった。「お母さんください」など、寺山演劇に共通したテーマ性もここにはある。また、全編に繰り返し現われるのは、当時歌われた歌謡曲への郷愁とオマージュである。それは、振り返ってみると、あまりにも安っぽい感傷なのだが、寺山はあえてそれを歌うのだ。2014/08/25
新地学@児童書病発動中
104
寺山修司唯一の長編。登場人物たちはみんな孤独を抱えており、それはどんなことをしても解消されることはない。それでも他人とのつながりを求めて、ぎこちない触れ合いを求める彼らに自分を重ね合わせながら読んだ。ラストで新次がバリカンに何発もジャブを叩きつけるのは、人と人の間の埋めることのできない隔たりに対する怒りのような気がした。過ぎ去った昭和の匂いが甦って来る東京の場末の描写には強い郷愁を感じる。当時流行っていた広告や歌謡曲の取り入れ方も巧み。寺山修司が偉大な表現者だったことがよく分かる作品。2013/12/02
青蓮
97
猥雑な喧騒、犇めく人々、溢れる雑踏、拭いきれない血と泥の匂い。1960年代の新宿が舞台の物語。当時流行った映画や歌謡曲、実在している芸能人の名前、テレビCMのパロディ、著名な詩句、ジャズからの引用などを散りばめた本作は将に寺山ワールド全開。当時のことを明確に知らなくても不思議と懐かしさを覚える。吃音と赤面対人恐怖症の〈バリカン〉と少年院から出所した新次がボクシングジムで出会う。ボクサーとしての道を進んでいく2人と彼等を取り巻く訳ありな人々の人間模様とで物語は展開していく。2019/04/14
扉のこちら側
86
2018年245冊め。読メには未登録だが以前読了したハードカバーで森山大道の写真とコラボした版が迫力満点であったため、この表紙は惜しいと思ってしまう。高度成長期のとにかく前へ前へという日本の衝動が感じられるが、物語の展開としては登場人物が多いためかもたついた印象もある。新宿新次「解説なんか聞きたかねえよ。俺には俺の読み方があるんだ。」2018/07/01
ワニニ
65
映画公開に合わせ再読。1960年代の昭和、新宿の風景、猥雑な雰囲気、そしてテラヤマワールドのコラージュ。母を喪っている若者たちが、“荒野”で、何とか自分の存在を確かめる為、もがく青春。孤独と熱が渦巻いている。今尚、いや現代だから?さらに?、鋭く洗練された言葉が刺さる。2017/10/09
-

- 電子書籍
- ざんねん!ねこ旅館【話売り版】10 ペ…
-
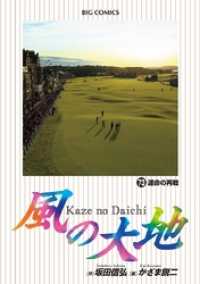
- 電子書籍
- 風の大地(73) ビッグコミックス







