内容説明
一筋に学問に打ち込み業績をあげながら、社会的評価を得られない研究者の凄まじい情熱と怨念をテーマにした短編集である。延喜式の廃字の意味・戦争中の人体実験・新興宗教の弾圧事件・邪馬台国の謎の究明などに人生を賭ける男たちの行状に、自らの孤独な執念を重ねる出色の清張サスペンス。彼らを見放す女たちや頑迷な学会の様相を、昭和30年代日本の風景と共にきめ細かく描いた名品揃い。初文庫化作品を含む4編を収録。
著者等紹介
松本清張[マツモトセイチョウ]
1909年福岡県に生まれる。53年、『或る「小倉日記」伝』で、芥川賞を受賞。56年、朝日新聞社広告部を退社し、作家生活に入る。67年、吉川英治文学賞、70年、菊池寛賞、90年、朝日賞を受賞。92年8月没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
竹園和明
41
世間に認知されない事への恨みを抱く研究者らを描いた3編。『皿倉学説』は、自らの失態で妻に去られ、新たな愛人にも軽視される日々を送る脳生理学者の物語。その主人公採銅は、奇妙な学説を唱えた地方の無名医者に興味を抱く。周りの者に冷笑されながらも学説の裏付けを独り調べて行くうち、ある重大な仮説に辿り着く。それに気付いた時の男の困惑、動揺、高揚の筆致がスリリング。自分だけが真実に気付いているのだという自負心が、自分を蔑ろにする者達への怨念へと変わっていく様子が怖い。長編だったら深みも加わり、傑作と謳われたはずだ。2024/07/31
sashi_mono
19
一般に「学究モノ」と呼ばれる清張の中短編4作を収める。既読の「笛壺」と「陸行水行」のほかに、世間から忘れられつつある脳神経学者の孤独な内情に追った「皿倉学説」、大本教の弾圧事件を特高の側から描いた「粗い鋼板」といったラインナップ。「皿倉学説」が一等いい。2020/03/25
にせものばかり
11
清張さんの短編集ですがミステリー色は薄いです。新興宗教や邪馬台国の研究に尽くした人物にスポットを当てた作品です。2014/03/01
とめきち
9
『皿倉学説』「脳性理学」といういままで自分が触れたことのない分野の話だったが、興味深く読めた。「実験に用いた猿の体重は六〇キロ」という辺りからグッと面白くなった。まさかという恐怖と好奇心で、先が気になって仕方なかった。ただ、裏表紙には、そのまさかの想像をたった一言でネタバレしており興ざめだった。先にここを読まなくて良かった。せっかく清張さんは言葉を選びながら慎重に物語を進行していたのに!主人公の採銅教授を取り囲む悪妻や出来の悪い愛人、ナメた態度をとる元弟子などを本当に憎らしく描いており採銅教授に同情した。2024/04/08
koji
9
松本清張記念館に行ってきました。ファンには堪らなく、いくら居ても飽きません。さて本書です。「陸行水行」を読みたくて、図書館から借りました。邪馬台国の推理は、「古代史疑」に待ちたいと思いますが、STORY展開には引き込まれます。特にラスト。古びた漁船を漕いで「邪馬台国」をめざす二人は、思わず山口百恵「乙女座宮」の「二人の乗ったゴンドラ」を思い出してしまいました。その他「皿倉学説」以外は初読です。主人公の偏狂ぶりのは凄まじさ。呪縛に囚われる「笛壺」、煩悶しながら時代に翻弄される「粗い網版」。読み応えがあります2015/08/23
-
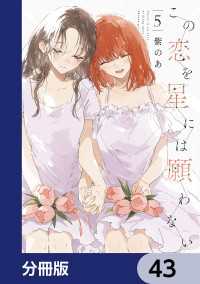
- 電子書籍
- この恋を星には願わない【分冊版】 43…







