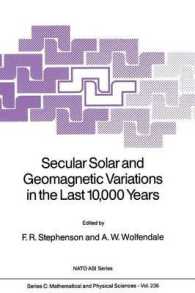- ホーム
- > 和書
- > エンターテイメント
- > TV映画タレント・ミュージシャン
- > ミュージシャンの本
出版社内容情報
ファン必携。YMO1978-2043。「2043」の秘密は本書の中に。
内容説明
ファン必携のYMO完全ヒストリー。いままで知られていなかった新事実も満載。
目次
第1部 1978‐1983(『イエロー・マジック・オーケストラ』その誕生の背景にあったもの、変転していく運命;イエロー・マジック・オーケストラ、ついに世界へ;イエロー・マジック・オーケストラの新しいステージ『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』;初のワールド・ツアーと人造美のライヴ・アルバム『パブリック・プレッシャー』;スネークマンショーとのコラボレーションが生んだYMOの異色作『増殖』 ほか)
第2部 1992‐2021(『テクノドン』の目覚め;Live in TOKIO Dome;20世紀の終わりに―奇貨としてのスケッチ・ショウとHAS;YMO環境21世紀;実質的な再々結成。「ライディーン79/07」 ほか)
著者等紹介
吉村栄一[ヨシムラエイイチ]
1966年福井市生まれ。月刊誌『広告批評』(マドラ出版)編集者を経てフリーランスの編集者、ライター、コピーライターに。2014~2015年には松武秀樹氏とともに『YMO楽器展』、2018~2019年にかけて牧村憲一氏、高野寛氏とともに『イエロー・マジック・チルドレン』一連企画をプロデュース(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ken D Takahashi
10
約40年前の僕が、このバンドに興味を示さなかったら恐らく今の僕の音楽の好みはかなり変わって居たと思う。時系列をおって丁寧に綴られた「YMO歴史本」であります。随分長い時間このバンドを見聞きして居りますが、そんな僕でも充分楽しめて納得出来る一冊でありました。5年程の実働期間よりも、解散(散開)後の期間の方が長くて面白い。つくづく不思議なバンドなのであります。現在闘病中のお二人を気にしつつ、次は「音」で楽しませて戴きたいです。2021/03/21
bumps
2
YMO のデビュー前のミュージシャンや音楽業界の動向など背景も含めて語られている本書。 そうだったのかという余談もふんだんに散りばめてあり、YMOフリークは十分楽しめる内容だと思う。 1978年のデビューから1983年の散開まで、紆余曲折あったのは、多くの人が知るところだが、個性の衝突に苦しみつつも、YMOで音楽を創ることの意味を追求して取り組んだ時期も結構あったのだということが分かる。 この本を読んで、BGM, テクノデリックを聴き込んで見たくなった。2023/04/21
almondeyed
2
この本を読んでいて、なるほどそうだなと思ったのが、この3人はそれぞれバックグラウンドや関心事が違うのに、常に新しい事に挑戦し続けているところが共通している。そして常に彼らよりも下の世代のミュージシャンたちと波長が合っていく。そこがまたおもしろい。2023/01/08
Kolon
1
YMOの歴史が現代に至るまで詳しい取材や情報に基づき網羅的に書かれており楽しく読めた。 知り合いが沢山出て来たが、彼らが果たした役割も良く理解出来た。 YMOへの愛情が突き抜けた本である。2021/05/17
Nepenthes
0
YMOファンならばおおよそ周知の内容であるけれども、スケッチショウ以降の動向・インタビューをこうしてまとめて読めるのが嬉しい。しかし欲を言えば、個人的にはそろそろYMOの楽曲や背後関係を理論的・歴史的に分析してまとめた本が読みたい。楽曲一つとっても非常に興味深いアイデアが満載であることは音楽的にある程度の造詣を持っているのであれば理解出来ることだし、そちらの需要も多いと思う。どんなに分厚くなろうが中身の濃いものになることは必然だし、資料的価値も大きいものになるのでは…と読中何度か思い描いた。2022/04/02
-

- 和雑誌
- ブレーン (2026年1月号)
-
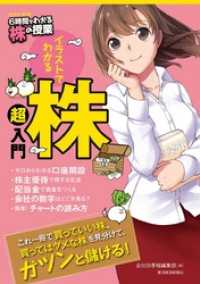
- 電子書籍
- がんばる!かぶ 6時間でわかる株の授業