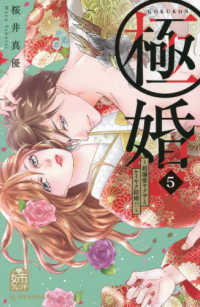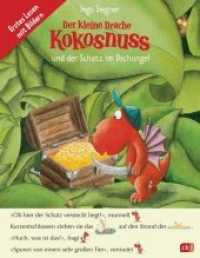内容説明
貧窮と性病、不遇と冷笑の中で自らの“文士道”を貫いて書き、無念に散った無頼の私小説家・藤澤清造。その短くも不屈の活動期間に残した玉石混交の作品群から、歿後弟子・西村賢太が厳選、校訂。商業誌初登板の、伸るか反るかの情熱が作の巧拙を超えて迫りくる「一夜」、抱腹絶倒の借金文学の傑作「刈入れ時」、故郷で危篤に陥った母の死を貧ゆえに切望する「母を殺す」、新発見原稿「敵の取れるまで」等、戯作精神に富む十三篇を収録。
著者等紹介
藤澤清造[フジサワセイゾウ]
1889年10月、石川県鹿島郡(現・七尾市)生まれ。尋常高等小学校卒。足の骨髄炎手術後の自宅療養を挟み、七尾町内で各種職業に就く。1906年上京。『演芸画報』誌訪問記者等の職を経て、22年、書き下ろし長篇小説『根津権現裏』を刊行。新進作家の列に加わるが、程なく凋落。長年の放埒な悪所通いにより精神が破綻。警察に勾留、内妻への暴力行為が続いた果てに、32年、厳寒の芝公園内ベンチにて狂凍死する
西村賢太[ニシムラケンタ]
1967年7月、東京都江戸川区生まれ。中卒。刊行準備中の『藤澤清造全集』(全五巻別巻二)を個人編輯。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
孤独な建築家の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
青乃108号
98
これもまた大変マイナーな本。西村賢太による、西村賢太の為の藤澤清造短篇集。西村の藤澤に対するリスペクトが十分に伝わってくる。後の西村の小説に引き継がれる、金がないあまりの貧乏話と女の話ばっかり。毎日少しずつ読んだけど、大して面白いとは思えず。唯一「刈入れ時」の間抜けな旦那の、嘘八百ならべて金策に奔走する間抜けな顛末には、腹を抱えて笑ったけれども。この短編だけは話のスピード感といい、どんどん悪くなる展開といい、予測通りにオチをつけてくれて読み手の期待を裏切らない点で、記憶に残りそうな作品なのだが、他は今いち2023/08/07
東京湾
9
「僕達貧乏人には、それ自体もう安寧なんか与えられちゃ居ないんだからな。安寧なきわれらに、何んの秩序かこれ要せんやだ」貧窮への怨嗟、飢え乾く欲望、閉塞と孤独、とにかく金、金、金がほしい。大正文壇の片隅で顰蹙を買いながらも己の文士道を貫き、貧困と病と狂気の果て、日の目を見ることなく凍死した作家・藤澤清造。その魂がおよそ90年を経て、歿後弟子・西村賢太の編纂の元よみがえる。生々しい窮乏の有様と、それにどうにか抗わんとする精神の切実な叙述が印象的だった。貧窮の極限とも言える「母を殺す」が特に胸に残る。2020/01/15
東
3
西村賢太が絶賛の作家。西村氏が歿後弟子まで名乗る書き手、藤澤清造。 この本は、貧乏に喘ぐ様々な人におススメの一冊です。 と言いたいところですが、内容は幼稚な自業自得人間のルサンチマン愚痴文句劇場。 どうでも良い内容をダラダラ何ページも書いている点は構成力の無さを露呈している。 そういった点は「根津権現裏」も同様だが。 と、こき下ろしたが「刈入れ時」のような借金クズ野郎の一日と顛末は抱腹絶倒だし。 嫌いな相手を、いちいち豚だの犬だの表現している様は、読んでいて痛快でニヤついてしまう。 読み手を選ぶ作家です。2022/12/24