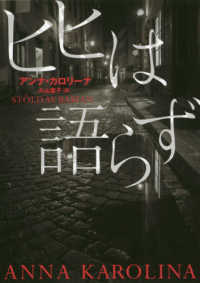出版社内容情報
元国税調査官が5000年の歴史にガサ入れ!
「ローマ帝国は“脱税”で滅んだ」「ナポレオンは“金融破綻”で敗れた」――お金の流れを読むだけで、歴史はよくわかる、さらに面白く見えてくる!「お金」「経済」「権力」の5000年の動きを徹底的に追跡調査!
序 「お金の流れ」で読み解くと、「世界史の見え方」はガラリと変わる!
第1章 古代エジプト・古代ローマは“脱税”で滅んだ
第2章 ユダヤと中国――太古から“金融”に強い人々
第3章 モンゴルとイスラムが「お金の流れ」を変えた!
第4章 そして世界は、スペインとポルトガルのものになった
第5章 海賊と奴隷貿易で“財”をなしたエリザベス女王
第6章 無敵のナポレオンは“金融戦争”で敗れた
第7章 「イギリス紳士」の「悪徳商売」
第8章 世界経済を動かした「ロスチャイルド家」とは?
第9章 明治日本の“奇跡の経済成長”を追う!
第10章 「世界経済の勢力図」を変えた第一次世界大戦
第11章 第二次世界大戦の“収支決算”
第12章 ソ連崩壊、リーマンショック――混迷する世界経済
内容説明
元国税調査官が5000年の歴史にガサ入れ。たとえば―ローマ帝国滅亡は「脱税」が原因だった!楽しく読むだけで歴史の本質がつかめる。
目次
古代エジプト・古代ローマは“脱税”で滅んだ
ユダヤと中国―太古から“金融”に強い人々
モンゴルとイスラムが「お金の流れ」を変えた!
そして世界は、スペインとポルトガルのものになった
海賊と奴隷貿易で“財”をなしたエリザベス女王
無敵のナポレオンは“金融戦争”で敗れた
「イギリス紳士」の「悪徳商売」
世界経済を動かした「ロスチャイルド家」とは?
明治日本の“奇跡の経済成長”を追う!
「世界経済の勢力図」を変えた第一次世界大戦
第二次世界大戦の“収支決算”
ソ連崩壊、リーマンショック―混迷する世界経済
著者等紹介
大村大次郎[オオムラオオジロウ]
元国税調査官。国税局に10年間、主に法人税担当調査官として勤務。退職後、ビジネス関連を中心としたフリーライターとなる。一方、学生のころよりお金や経済の歴史を研究し、別のペンネームでこれまでに30冊を越える著作を発表している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハッシー
こも 旧柏バカ一代
Miyoshi Hirotaka
Kentaro
ぴー