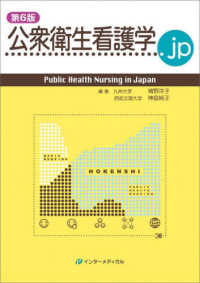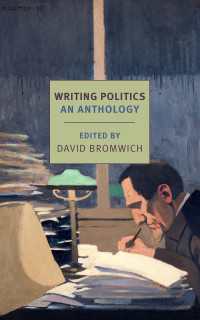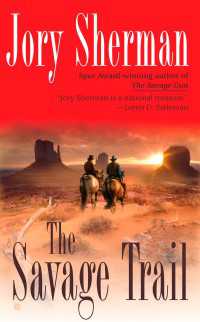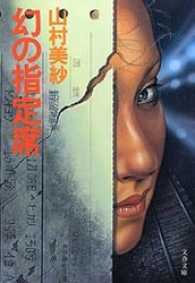出版社内容情報
日本の老後生活を巡る問題は、公的年金の信頼性、退職後の生活資金、介護や医療サービスの確保、医療技術の進展といった多岐にわたるテーマを抱えています。特に、老後の生活資金の大部分は公的年金で賄えるかどうかがポイントであるものの、政府が公表する年金の財政見通しでは、様々な将来見通しを公開しているが、非現実的な仮定を置くことによって、真の問題を覆い隠しています。
老後資金の必要額に関しては、2019年の「老後資金2000万円問題」以来、個人の貯蓄や投資の重要性が注目されていますが、本書では、株式投資や新NISAなどに頼るより、自己投資によるスキルアップがより効果的であると経済学者の野口悠紀雄氏は提言。また、団塊ジュニア世代は就職氷河期を経験し、雇用環境が厳しいなか、65歳時点で3000万円以上の資金が必要になる可能性も出てきています。
さらに、高齢者の医療保険や介護保険負担も増加しており、「所得」ではなく「資産」に基づく負担制度が必要だと野口氏は指摘。
重要なのは、若いうちからできうる限りの努力をして、老後の備えをしておくこと。また、老後のことについて、他人事ではなく、「自分事」として考えることです。
老後の暮らしや資金について考え直してみるのに最適な1冊です。
『終末格差』 もくじ
序章 広がる終末格差
第1章 老後資金としていくら必要か?
第2章 投資戦略で老後を守れるか?
第3章 団塊ジュニア世代がこれから直面する厳しい老後
第4章 公的年金は老後生活の支柱となるか?
第5章 介護保険は破綻しないか?
第6章 期待される医療技術の進歩
第7章 高齢者の負担増が進む
第8章 終末格差を克服するのは、自分への投資
内容説明
近年の物価高騰に加え、医療保険や介護保険は高齢者の負担が増加し続け、年金だけで老後生活を送ることは到底できない。経済的にも精神的にも幸せな終末を迎えるためのヒントを、経済学者の野口悠紀雄が指南する。
目次
序章 広がる終末格差
第1章 老後資金としていくら必要か?
第2章 投資戦略で老後を守れるか?
第3章 団塊ジュニア世代がこれから直面する厳しい老後
第4章 公的年金は老後生活の支柱となるか?
第5章 介護保険は破綻しないか?
第6章 期待される医療技術の進歩
第7章 高齢者の負担増が進む
第8章 終末格差を克服するのは、自分への投資
著者等紹介
野口悠紀雄[ノグチユキオ]
一橋大学名誉教授。1940年東京生まれ。63年東京大学工学部卒業。64年大蔵省入省。72年エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを歴任。専攻はファイナンス理論、日本経済論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mazda
まゆまゆ
訪問者
チョビ
みんな本や雑誌が大好き!?