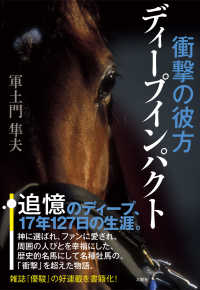出版社内容情報
他人から好かれる人は「問い」を使いこなしていた。
コミュニケーションの課題を解決する「考え方」「話し方」が身につく!
仕事・学校・家庭で使える対話の技法を徹底解説。
意見の合わない人と、どうコミュニケーションをとれば良いのか。人間関係を保ちながら、誤りを指摘するためには、何と伝えるのが望ましいのか。気鋭の哲学研究者が、日常の問題を解決する「問いの技術」を徹底解説する。現代のための、実践的なコミュニケーション術。
【目次】
はじめに
第1章 対話とは何か
第2章 対話の魂としての「問い」
第3章 〈深い対話〉に向けて
第4章 対話のさまざまなシチュエーション
第5章 対話的思考の応用
おわりに
【目次】
はじめに
第1章 対話とは何か
第2章 対話の魂としての「問い」
第3章 〈深い対話〉に向けて
第4章 対話のさまざまなシチュエーション
第5章 対話的思考の応用
おわりに
内容説明
カギは疑問文にあった!意見の合わない人と、どうコミュニケーションをとれば良いのか。人間関係を保ちながら、誤りを指摘するためには、何と伝えるのが望ましいのか。気鋭の哲学研究者が、日常の問題を解決する「問いの技術」を徹底解説する。現代のための、実践的なコミュニケーション術。
目次
第1章 対話とは何か(対話・議論・会話の違い;「対話をする」とは何をすることか?;「一人称的経験」とは何か?;「一人称的経験」を共有するための問い)
第2章 対話の魂としての「問い」(対話は「問い」で回る;対話における心構え1―「二人称的関心」を持つこと;対話における心構え2―「一人称的探究」を行うこと;傾聴・尊重・共感について)
第3章 〈深い対話〉に向けて(対話の三つのルール;対話の六つのポイント;「対話が深まる」とはどういうことか?1―問いと答えの連鎖;「対話が深まる」とはどういうことか?2―「根本的な問い」の発見)
第4章 対話のさまざまなシチュエーション(フラットな関係の対話か、上下関係のある対話か;個人間の対話か、複数人の対話か;固定的な環境の対話か、流動的な環境の対話か;対面の環境での対話か、オンラインの環境での対話か)
第5章 対話的思考の応用(対話的に議論する;対話的に会話する;対話的に思考する)
著者等紹介
山野弘樹[ヤマノヒロキ]
1994年、東京都生まれ。2025年、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻(比較文学比較文化分野)博士課程修了。博士(学術)。千葉工業大学非常勤講師。専門は哲学(とりわけポール・リクールの思想)。2019年、日本哲学会優秀論文賞受賞。2021年、日仏哲学会若手研究者奨励賞受賞。また、哲学研究者の立場からVTuber文化に関する研究も行なっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。