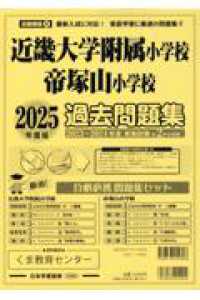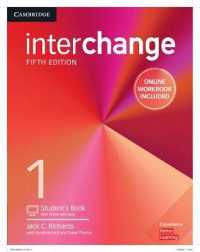出版社内容情報
観光マーケティングはズレている。
すぐ模倣され、汎用品・低価値にされる時代。高付加価値、差別化の鍵は「歴史」にこそあった。
大事な点はハード(城や古民家)だけが歴史文化ではないこと。歴史とは模倣できない地域性だ。文献資料などのソフトこそ、地域ブランドを生む無形資産として大きい。経済的価値のみ重視し、歴史文化を破壊する手法は否定し、各地で観光と歴史文化の共生に取り組む実践者にして研究者が実例を基に理論と手法を具体的に解説する。
■ブランドの創出とは、「勝つための競争」から「負けないための競争」へ転換すること。
■認知拡大だけでは需要は生まれない、歴史的景観だけでは消費につながらない
■ハードはいずれコモディティになる
【目次】
はじめに――コモディティ化が進む世界
第一部 観光によるヒストリカル・ブランディング
第一章 保存vs.開発を超える――北海道小樽運河
第二章 無形価値を可視化する――千葉県佐原の大祭
第三章 ヒストリカル・ブランディングの理論――観光による地域ブランディング
コラム一 歴史文化観光を推進しても上手くいかない――失敗の検証一
第二部 商品開発による地域ブランディング
第四章 地場産業のブランド化――千葉県横芝光町の大木式ソーセージ
第五章 ファンコミュニティによるブランディング――熊本県菊池市の菊池一族
第六章 ヒストリカル・ブランディングの理論――商品開発による地域ブランディング
コラム二 歴史文化観光を推進しても上手くいかない――失敗の検証その二
第七章 ヒストリカル・ブランディングの持つ可能性――イノベーションを起こす歴史活用
コラム三 実践する上での注意事項
終章 「勝つための競争」から「負けないための競争」へ
おわりに
主要参考文献一覧
内容説明
歴史とは模倣できない地域性である。相変わらずのハード(箱もの)頼みなど、観光マーケティングはズレ続けている。すぐに模倣され、「どこにでもあるモノ」にされる時代に脱コモディティ化を実現し、地域ブランディングの差別化を成すコアは商業主義と離れた「歴史」にあった。特に文書などのソフトこそ、大きい。各地で歴史文化と観光の共生に取り組む研究者・経営者が、無形価値を可視化する方法などを具体的に解説する。
目次
第1部 観光によるヒストリカル・ブランディング(保存vs.開発を超える―北海道小樽運河;無形価値を可視化する―千葉県佐原の大祭;ヒストリカル・ブランディングの理論―観光による地域ブランディング)
第2部 商品開発による地域ブランディング(地場産業のブランド化―千葉県横芝光町の大木式ソーセージ;ファンコミュニティによるブランディング―熊本県菊池市の菊池一族;ヒストリカル・ブランディングの理論―商品開発による地域ブランディング;ヒストリカル・ブランディングの持つ可能性―イノベーションを起こす歴史活用;「勝つための競争」から「負けないための競争」へ)
著者等紹介
久保健治[クボケンジ]
1981年、東京都中野区生まれ。(株)ヒストリーデザイン代表取締役。武蔵野大学・神田外語大学兼任講師。NPO法人全日本ディベート連盟専務理事。データストラテジー(株)研究員。創価大学大学院文学研究科人文学専攻博士後期課程単位取得満期退学。修士(歴史学)。当時の専攻は近代日本政治史、演説討論教育史。近代日本史料研究会、藤沢市史の史料編纂に従事した後、東京工業大学特任講師、ソーシャルメディアマーケティング会社を経て(株)ヒストリーデザインを設立。現在、大阪市立大学大学院経営学研究科博士後期課程にも在学し、経営学者でもある。専門は地域マーケティング論、経営戦略論、地域資源論。経営学者兼コンサルタントとして、観光分野を中心に歴史を活用した経営戦略の理論研究とビジネス実践を行っている。ライフワークとしてコミュニケーション教育にも従事。企業研修や国内及び東アジアで日本語ディベートの指導者育成にも携わっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえぽん
雲をみるひと
oyoide
takao
Toshiaki
-
![モーニング 2015年49号 [2015年11月5日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0285619.jpg)
- 電子書籍
- モーニング 2015年49号 [201…



![2nd GIG『ANAMNESIAC[アナムネージアック]』](../images/goods/ar2/web/imgdata2/49114/4911463171.jpg)