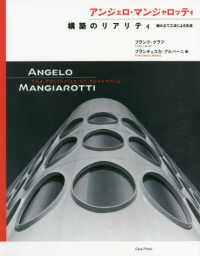内容説明
母の郷里ですごした、少年時代の夏休み。そのなんでもない田舎ぐらしの中でぼくは幻とも現実ともつかない不思議なできごとに出会う。昭和三十年代を舞台につづる12の奇譚。小学校高学年から。
著者等紹介
斉藤洋[サイトウヒロシ]
1952年、東京都に生まれる。中央大学大学院文学研究科修了。現在、亜細亜大学教授。1986年『ルドルフとイッパイアッテナ』で講談社児童文学新人賞を、1988年にはその続編『ルドルフともだちひとりだち』(講談社)で野間児童文芸新人賞を受賞。1991年、路傍の石幼少年文学賞を受賞
森田みちよ[モリタミチヨ]
愛知県生まれ。イラストレーター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちょろこ
123
畳に寝転びながら読みたい一冊。あれは何だったんだろう…著者の不思議でちょっぴり怖い夏の思い出話。夏の風、音を感じ、思わず畳に寝転びたくなった。扇風機があればなお最高っていうぐらい田舎の夏が溢れていたな。少年だから出会えて、体験できたこと。それは蝉の声が止む一瞬の静寂を合図に陽炎のようにゆらめいて、あちらとこちらの世界が交差する瞬間の数々だったのかもしれない。「新盆の夜」の木のイヌが印象的。束の間の攻めと守りが薄ら寒く背筋を伝った。二度と戻らない時間、思い出が逃げないように記す作業も素敵だと思いながら読了。2024/07/05
mocha
103
子どもの頃、夏休みのたびに出かけた母の実家。其処ここに不思議なものたちの気配があって、でもどうやらそれが見えるのは僕ときっつあんだけらしい。狐に幽霊、座敷童子、沼目…。昭和30年代の日本の田舎。もしかしたら斉藤洋さんの体験談も盛り込まれてるのでは?こんな少年だったから、あんなお祖父さんの孫だから、わくわく不思議なお話を次から次へと書けるのに違いない。2016/09/26
ままこ
79
舞台は昭和30年代。子供の頃夏に訪れていた母の郷里。そこで、いくつもの奇妙な体験をする。意表をつく神隠し。新盆の本家でのあの場面はゾッとする。黒い木の犬がいてホッとした。伝承を語るのが好きだった祖父。なるほど、そういう人だったのか。きっつぁんも不思議な人だった。読みやすい文体から郷愁を含む情景が自然と浮かんでくる。村に溶け込むように何かいる。トトロもいそう。聡く感知する能力に長けていたけど子供らしい面もちゃんとあるのが良い。装丁、見開きで描かれる挿絵も雰囲気を盛り上げる。夏にぴったりの遠野物語ような物語。2024/07/23
さつき
63
夏休みのたびに母親の実家に滞在する男の子の話し。きつねや座敷童子など子供しか見えない不思議が語られるかと思えば、没落していく本家と、成り上がりたい伯父さんとの駆け引きのような生臭い状況も描かれる。私の母の実家も当時は本家と呼ばれていて、私には分からないたくさんの人が常時出入りしているような家でした。子供は何も分からないと大人は考えるかもしれないけど、周囲の人の行動や言葉の切れ端から結構分かるものです。現実と怪異の狭間に生きるきっつぁんのような人も昔はたくさんいたんだろうな。昔懐かしい気持ちになる本でした。2024/09/14
ケイト
61
蚊取り線香の匂いと蝉しぐれ、青い空と白い入道雲、心の片すみにしまい込んだ夏休みの風景がよみがえる。井戸で冷やしたスイカの美味しかったこと。少年が結界の向こう側に見た不思議な光景、ノスタルジックな世界へと引き込まれた。田舎の因習とか好きじゃないものもあるけれど、何かを畏れる心。こういう話はとても好き。 2024/07/13