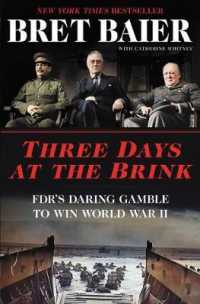出版社内容情報
2020年から2年半、特派員として現地に暮らし、イランの実体を追ったノンフィクション。国にはびこる真の「悪」とはいったいなにか。世界最大のテロ支援国家、嫌米国家の動きから米中ロの覇権争い、世界の勢力図の実相が見えてくる。
内容説明
世界最大の「テロ支援国家」、反米国家・イランでいったい何が起きているのか。イランを知れば米中ロの争いの行方、世界の勢力図の変化が見えてくる。制裁の影響で貧困にあえぎ、不満を溜める国民たち。そんな国民を抑圧し、核開発を進める国側。イランに漂う「悪」の正体を追う。
目次
序章 イランは「悪」なのか
第1章 反米国家
第2章 ソレイマニの素顔
第3章 史上「最低」の大統領
第4章 瀕死の核合意
第5章 制裁がもたらした影響
第6章 貧窮にあえぐ国民たち
第7章 抑圧の象徴・ヒジャブ
終章 揺れ続けるイラン
著者等紹介
飯島健太[イイジマケンタ]
1984年埼玉県生まれ。2007年、早稲田大学を卒業後、朝日新聞社に入社。奈良・高松の各総局、大阪社会部で主に事件や災害を取材。2017~18年にイギリスのロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS)国際政治学修士課程に在籍し、修了。2020年4月、テヘラン支局長に就任後、同年10月から2023年1月まで同支局に赴任。2023年2月から大阪社会部で事件を中心に取材している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
105
朝日新聞記者としてイランに駐在し「このような態度をイランに取らせるのは、イランを「悪」と断じて米英が圧力を加えてきた一つの結果。「悪」と断じられた側で真っ先に酷い目にあわされるのは一般の人々である」と語る著者の思いが伝わってくる。確かに、ライシ大統領の強権的な政治に問題は多いが、古くはモサデグ政権追放のクーデターに始まり、ソレイマニ司令官殺害、核合意からの一方的な離脱など、米国に、イランを「悪の枢軸」と名指しする資格があるのかと問いたい。新興の米国と較べ、ペルシャ帝国のもつ大国の風格に、私は共感を覚える。2024/05/28
れい
6
【図書館】今の生活と対比した時に、余りにも遠くの異国で起こっていることであり、自分とはほぼ関係ないことを学んでどうするのかという疑問が何度もよぎった。人間というものはどの人種、どの民族であっても、根底は同じらしい。国家の頂点に立つものは、自国(或いは自分)に優位になることであれば、大抵のことは容赦なくカードを切ってくるらしい。悪とは何なのか。どの立場から物を見るかによって異なる。イランから見ると強国の言いなりにはなりたくない。ただ国民や難民が気の毒である。私は何もしてあげることができない。無力だなぁ。2024/08/12
ポルポ・ウィズ・バナナ
5
◎イラン革命は「腐敗したエスタブリッシュメント層への反動」であることと「アメリカと癒着した王政への反動」であることが意外と頭の中で別になってた。ついでにいうと、イラン革命前のカラフルな洋装を身に纏ったテヘランの女性たちも前述のことを踏まえると複雑な気持ちになる。◎トランプ指示によるソレイマニ氏殺害の問題と根深い。著者はソレイマニが「テロ組織であるハマスとの繋がり」を問題視しているフシがあるが、同時に国民にとっては彼がISの侵攻から国を守った英雄であることも記している。2024/06/23
K
4
2020年から3年弱、目まぐるしい情勢変化を現地イランで取材した記者によるルポ。米中露に翻弄される中、周辺諸国間で起こる衝突や過酷な環境問題により逼迫していく国内経済、政権交代によって確立したイスラム体制とそれに対して自由を求める抗議デモの広がり、力による支配の拡大と犠牲になる一般国民。どこから手をつけたらいいのかわからないながらもまずは「相手を理解すること」から始めるのが第三国としての態度だと思われる。2024/08/20
お抹茶
4
米軍に殺害されたイスラム革命防衛隊のソレイマニ司令官について,祖国をISの侵略から守ったと慕い,その死に泣くイラン人は珍しくない。その英雄を殺害した悪党・米国に対する憎しみは深い。2021年の大統領選挙ではライシが当選したが,投票率は過去最低で,無効票数は多く,革命体制への不信任は強い。制裁による物価上昇は,体感では年に2~4倍以上。革命体制の中枢にとって国側に不満をいう人達は暴徒であり,その排除は国民の人権を守る正義とされる。イランと米国,イラン内での強硬派と女性など,考え方の違いが絶望的に大きい。2024/06/12
-

- 電子書籍
- 真・上京シェアハウス~彼女と幼馴染と知…
-
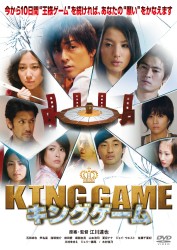
- DVD
- KING GAME キングゲーム