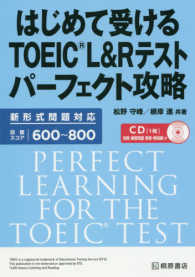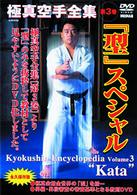出版社内容情報
国立大学が法人化されて20年。この転換は大学にどのような影響を与えたのか。朝日新聞が実施した学長と教職員へのアンケートに寄せられたのは悲鳴にも近い声だった。東大の学費値上げ問題の背景など、国立大で起きている真相に迫る。
内容説明
現場から寄せられる窮状や疲弊ぶり。彼らの声はまさに「悲鳴」だった―。「国立大学は、国から予算をもらって安穏としているのだろう」いまだにそうした見方を持つ人は多い。しかし、法人化から20年の間に引き起こされたのは、そうしたイメージとは、あまりに異なる現実だった。長年にわたる取材で浮き彫りになった、法人化とその後の政策がもたらしたあまりに大きな功罪とは―。
目次
第1章 国立はなぜ“残酷立”と揶揄されるのか
第2章 研究をする時間がない研究者たち
第3章 不安定化する雇用
第4章 低下する教職員のモチベーション
第5章 誰が「大学の自治」を奪うのか
第6章 持続可能な国立大学とは
著者等紹介
増谷文生[マスタニフミオ]
1971年栃木県出身。1994年入社。2005年から東京社会部で教育、主に大学関連の取材を担当。仙台、京都両総局でのデスク業務などを挟み、17年から再び社会部で教育を取材。20年から論説委員を兼務
山本知佳[ヤマモトチカ]
1991年広島県出身。2014年入社。名古屋報道センターなどを経て、22年から東京社会部で教育取材を担当。主に文部科学省で、大学や小中高などの教育行政を中心に取材(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gonta19
kan
おさむ
スプリント
awe
-

- 和書
- 追放薬師は人見知り!?
-
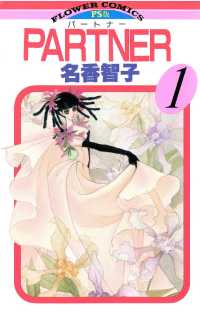
- 電子書籍
- PARTNER(1) フラワーコミックス