出版社内容情報
五・一五事件の青年将校を「赤穂義士」になぞらえて世間は称賛した! 軍部とマスコミに先導された 大衆世論 の変遷から戦争への道筋を読み解く、最新研究に基づく刺激的な論考。ウクライナ戦争、米中対立など国際情勢が緊迫化する今こそ読まれるべき一冊!
内容説明
戦前以来の日本における大衆・世論の強い圧力=「同調圧力」こそ、コロナ禍によって現代にも顕著に現れたこの国の政治・社会の特質である。「同調圧力」というのは大衆社会によって現れる。戦前日本の政治・社会の基底には極めて強い大衆社会化の圧力があり、多くの事件を引き起こしたが、これまで十分に検討されてきたとは言いがたい。本書ではこの点を重要な要素として取り込んで昭和史を検証している。
目次
「軍縮期」の軍人と世論―軍国主義台頭の背景
普通選挙と政党政治―疑獄・乱闘・「党弊」
無産政党の台頭と挫折
ロンドン条約・統帥権干犯問題
満州事変
血盟団事件、五・一五事件―公判と世論
国際連盟脱退
帝人事件
二・二六事件
日中戦争―勃発と拡大
三国同盟・ヒトラーと日本世論
近衛新体制と大政翼賛会
日中戦争をめぐる反英米論の展開
著者等紹介
筒井清忠[ツツイキヨタダ]
1948年大分県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位修得退学。博士(文学)。帝京大学文学部長・大学院文学研究科長。東京財団政策研究所主席研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
75
筑摩新書でやっていたことを朝日選書に移してきたようで、例によって編者の「はじめに」でひとくさりあるが、それが誰をさすのかは分からない。面白い論考もあったが、「最前線」というよりは、副題の大衆とマスコミの動きに焦点を当てた内容と捉えた方がいい。例えば大正期に軍人が苦境にあったたことが今まであまり論じられていないという(第1章)が、永田鉄山の評伝などにはしばしば論及されているのだが。また「15年戦争」という連続より1933~37年の断絶を重視する向きがある(第8章)が、連続の意味を取り違えていないか。2023/01/27
鯖
22
朝ドラで帝人事件をモデルとした裁判が取り上げられてたので、この本に章立てであったよなと手に取った本。筒井先生が編者ということもあり、全体的にポピュリズムに触れたものが多い。大衆世論マスコミの圧によって日本は戦争に突入していったというのはそりゃそうなんだろうけども、一方で言論弾圧や憲兵等が最も強かった時代な訳でその辺りの齟齬はどうなんだろな。安倍首相暗殺に絡めたいけど絡めないギリギリの論が多いなという印象。しかし515事件で死刑が出ないのってすごいな…。軍法会議の裁判官もつらそう。2024/05/20
CTC
15
昨年11月の朝日新書新刊。14章14著者の構成で、筒井清忠編。編者以外は70年代生まれの若い研究者を中心の執筆。「実証的研究の最新の成果」に基づき「大衆・世論の強い圧力」によって動いた昭和史を辿るというのが本書の眼目。ただ、いちばん気になったのは“十五年戦争”へのツッコミ。「今日の研究で」15年を「戦争一色で塗りつぶして理解することの危険性」の観点等から否定されている由をわざわざ2人の書き手が記しているが、わざわざ語るほどの研究成果なのかね。 2023/01/16
kenitirokikuti
11
図書館にて。同じ編者による、似たようなタイトルのちくま新書「昭和史講義」シリーズとともに借りた。本書の刊行年が2022年で、ちくまの方は2015年からである▲昭和史の見直しといえば、特に平成半ばの以降ともなれば、「新しい日本史教科書を作る会」的なテイストが連想されがちなのだが、戦後の昭和史が講座派マルクス主義と丸山眞男的近代主義に傾き過ぎてて…というか、例えば二・二六事件の裁判記録が閲覧可能になったの2016年だったりと、実証的な歴史学研究は進みきってはいない状態▲むつかしい分野なので理解が通らず。2024/08/12
かんがく
10
類書を読み過ぎてあまり新発見はない。副題の「大衆・軍部・マスコミ」にあるような、国民の軍隊観や英米観の変化が史料とともに紹介されている点は良かった。2024/05/08
-

- 電子書籍
- よくあるファンタジー小説で崖っぷち妃と…
-
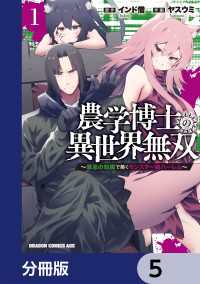
- 電子書籍
- 農学博士の異世界無双~禁忌の知識で築く…
-
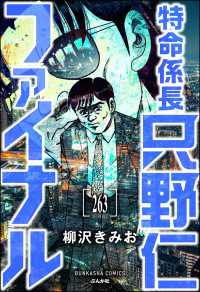
- 電子書籍
- 特命係長 只野仁ファイナル(分冊版) …
-
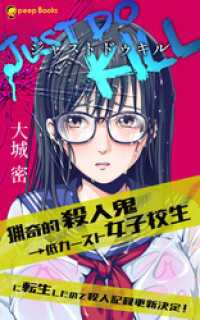
- 電子書籍
- JUST DO KILL~猟奇的殺人鬼…
-
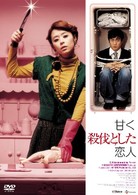
- DVD
- 甘く、殺伐とした恋人




