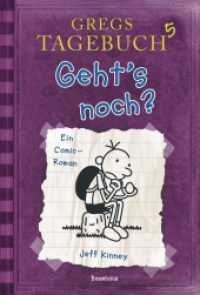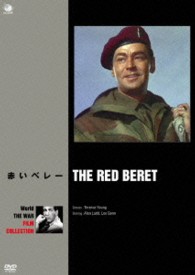出版社内容情報
優れた音楽はどのような作曲家たちの脳によってつくられ、演奏されているのか。ベートーベンからグールドまで、偉人たちの脳を大解剖。深い論理的思考で作られているクラシックの感動をとことん味わうための「音楽と脳の最新研究」を紹介。
内容説明
クラシックはなぜこれほどまでに人の心を動かすのか?優れた音楽を創り出す作曲家たちや、超絶技巧を繰り広げる演奏家たちの脳はどうなっているのか。音楽には、宇宙、数学との意外な関わり、そして科学の発展との密接なつながりがあった。深い論理的思考で作られているクラシックをとことん味わうための「音楽と脳の最新研究」を紹介。音楽が人の脳にもたらす意外な効用とは。
目次
第1章 音楽と数学の不思議な関係(音楽と科学の歴史;音の高さと数学;音の並び方と数学)
第2章 宇宙の音楽、脳の音楽(宇宙の音楽;脳の音楽)
第3章 創造的な音楽はいかにして作られるか(脳の記憶と作曲;脳の統計学習から作曲へ;脳に障害がありながらも卓越した曲を生む作曲家)
第4章 演奏家たちの超絶技巧の秘密(脳と演奏;演奏と脳の予測;演奏から生まれる個性;主観的な「価値」;知識よりも大切なこと)
第5章 音楽を聴くと頭がよくなる?(音楽と奇才;音楽の脳疾患への効果;音楽は私たちの心の中を「見える化」する)
著者等紹介
大黒達也[ダイコクタツヤ]
1986年、青森県生まれ。医学博士。東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構特任助教。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。オックスフォード大学、ケンブリッジ大学勤務などを経て現職。専門は音楽の神経科学と計算論。現代音楽の制作にも取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
1959のコールマン
原玉幸子
Isamash
Yappy!
-
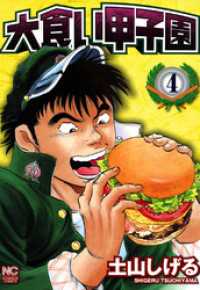
- 電子書籍
- 大食い甲子園 4