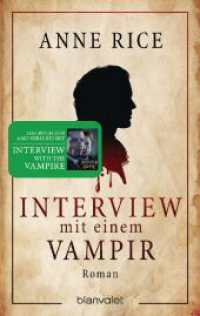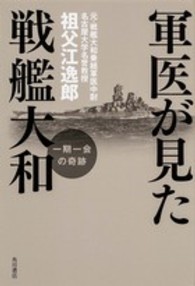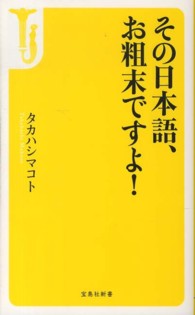出版社内容情報
岩間 敏[イワマ サトシ]
内容説明
戦後公開された機密資料を読み解き、今まで、ほとんど明らかにされてこなかった、開戦の過程と人造石油開発の実態に迫る。開戦判断の要因の一つは、国内の石油需給の見通しであった。これを大きく左右したのは人造石油の生産予測だった。政府・軍部の指導者も、人造石油に期待していた。しかし大本営政府連絡会議の席上、この計画は大きく変更される。そして航空燃料、物資輸送船舶の不足が明らかであるにも拘らず、この議論は行われないまま、開戦決定へ移行したことが分かるのである。
目次
第1章 日本を幻惑させたドイツの人造石油
第2章 開戦前の巨大プロジェクト、人造石油生産計画
第3章 日本周辺に石油供給源はなかったのか
第4章 開戦はどう決められたのか
第5章 人造石油はどのような役割を背負わされたのか
第6章 いつ頃から開戦の準備は進められたのか
第7章 困窮する石油需給と国民総動員の松根油生産
著者等紹介
岩間敏[イワマサトシ]
1946年、鳥取県生まれ。早稲田大学第一法学部卒。日本経済新聞社、トヨタ自販系研究所を経て石油開発公団(後の石油公団)に入る。通商産業省調査員、ハーバード大学中東研究所客員研究員、石油公団パリ、ロンドン事務所長、石油公団理事などを歴任。後、一橋大学大学院社会学研究科修士、博士課程修了(社会学博士)。現在、日本の近現代政治・軍事史を研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
CTC
7
10月の朝日新書新刊。著者は社会学博士、元石油公団理事。 昭和陸軍が油田開発の見込みがないのに満蒙と北中支の資源に拘り、結果国を誤る様には疑問があった。近年、当時最新の技術であれば、大規模油田発見も人造石油増産も目処の立つ話であった事が判ってきて、この種の新刊も連続している。本書は特に独が果たしながら日本が果たせなかった理由と、支那事変から終戦に至るまでの石油政策の変遷が詳しい。①独企業は石炭の直接液化の特許を持ち、操業もしていたが、“工業的技術”(連続操業可能なレベル)の確立は、実は今持って不詳と。2016/11/29
Meistersinger
4
石油が足りないことは分かりきってたので、人造石油開発へ。ドイツの先進的な技術には及ばず(ドイツのでも十分だったか疑問だけど)、頁岩油や松根油まで必死になって敗戦へ。2017/07/19
えるまぁ
3
軍ネタ好きならWWII時のドイツは空気から火薬を作り人造石油で燃料の不足を賄った話を知ってる筈。本書は日本の人造石油に焦点を当てている。いかにも日本的、軍開発部の面子優先で効率追求二の次な指示、「情けない(現実の)数字を出すな」と指摘者を左遷し粉飾を好む気質の上重点を人造石油からアルコールに松根油にと二転三転させる軍部、管理装置が直せずバルブを勘で制御する熟練工不在の銃後とぐったり。只思う、戦後70年経っても原発や豊洲問題とか同じ事やってるなと。戦争否定もいいけど戦争から学ぼうよ。だから私は軍事物を読む。2016/11/02
aeg55
2
戦艦大和の建造費8隻分もの巨大予算を注ぎ込まれた人造石油。大日本帝国海軍、そのものの醜態を表しているように思えた。『大東亜共栄圏の形成と崩壊』で悉く計画通りにいかない5ヵ年計画群があったが、この人造石油計画がかなりの部分を占めていたのであろう。人造石油自体も石炭を液化するものと頁岩から精製するシェールガスと2つあるが、何もさまざまなところで技術が追いつかず計画倒れに終わる。大日本帝国を象徴するような話である。2023/06/16
くらーく
2
希望で計画して、二進も三進もいかなくなって撤退というか敗戦。失敗の本質は変わらない。 こうやって振り返れば何とも愚かな事をと思うだろうけど、日本の組織の中に居れば仕方ないなあと思ったり。どうしてなんだろうねえ。2017/03/25
-

- 和書
- 碁の基本は定石