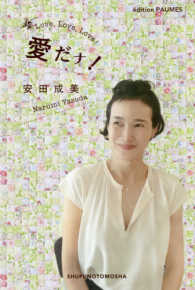出版社内容情報
喰らうは生きる。食べるは愛する。いっしょのご飯がいちばんうまい──水上勉の異色の食エッセイを原案に映画化した「土を喰らう十二ヵ月」を中江裕司監督自らがノベライズ。信州の里山で四季が移ろい、人が移ろう。四季折々の食で綴る人生ドラマ。
内容説明
長野の山荘にひとり暮らす作家のツトム。自ら畑を耕し旬の恵みを味わいながら、日々原稿に向き合う。そんな彼のもとを時折訪う編集者・真知子。四季折々の素材を料理し一緒に食べる特別な時間が過ぎていく―。水上勉の随筆から生まれた映画を監督の中江裕司がノベライズ。
著者等紹介
中江裕司[ナカエユウジ]
1960年京都府生まれ。映画監督。琉球大学入学を機に沖縄へ移住し、92年オムニバス映画『パイナップル・ツアーズ』の1編「春子とヒデヨシ」を監督。99年長編映画『ナビィの恋』が全国的に大ヒットし、同作で芸術選奨文部大臣新人賞を受賞。映画監督作品の他、テレビドキュメンタリーも多数。2005年には那覇市内の閉館になった映画館を「桜坂劇場」として復活させ、映画上映のほかライブやワークショップ等の文化発信にも携わる。沖縄のやちむん工房より直接買い付けも行っており、映画『土を喰らう十二ヵ月』でも器が使用されている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケンイチミズバ
97
私も思惑だらけの凡人です。暑い寒いの文句ばかり。自然を愛でる眼力もなし。真知子さんの心の中、会っている時は楽しい、離れると不安になる。そんなこんなを十年も続けている作家と編集者の二人がとてもいい。私ももうひと頑張りしてみようか。何をか?豪雪地で古い家を手直し土仕事をし、自給自足するうちに料理もうまくなって、おとなの女を喜ばせる。無理か。そもそも作家でもない。「私なんて身体の三分の二はコンビニでできているわ」「それでは生きていることにならないね」少し酔って会話が書くべきテーマに向かっていくこのシーンがいい。2022/11/30
はるを
65
🌟🌟🌟🌟🌟。映画鑑賞後に読了。俺は元々、映画ノベライズってあんまり好きじゃない。だからこの本も映画を鑑賞するまでは読むつもりはなかった。が、映画のストーリーがあまりにも良かったので手に取ってみた。俺は勉強不足でこの中江裕司監督は知らなかったのだけど、この人は凄い。自分の頭の中にあるイメージを映像化あるいはノベライズ化にする術をよく心得ている。120分ある映画の内容を的確でセンスのある言葉を散りばめて200ページ弱に纏めあげているスマートさに感服した。2022/11/25
えみ
46
人は死に向かって生きている。いずれ来る死を満たすために満たされた食事をとる。季節を感じる長野の山荘。自然を身近に、旬を喰らいながらひとりで暮らすツトムは小説家。素朴な生き方を書くことと、素朴に旬を食べること…2つの行為は一見華やかさとはほど遠く感じていたけれど、実は全くその反対で至極贅沢であることを目の前に突きつけられた気がした。時間の使い方、食を楽しむ意味、人との関わり方、生きる喜び、死に対する想い。本当の幸せはもしかしたらこんなところから自然に発生してくるのかもしれない。もっとこの暮らしを知りたい。2025/06/05
ちゃとら
44
気になっていた映画のノベライズ。妻の実家の長野に移住し、自給自足に近い生活をする作家のツトム。妻は難病で亡くなり、残された犬🐕さんしょと暮らす。幼少の頃、寺に入れられていたツトムが禅の作法を思い出しながら作る毎日の食がとても魅力的。自然の中の田舎暮らし、憧れるが私にはできない。義母の葬儀の後に思いついて焼いた骨壷は、自身の病の後に梅干し入れになる。愛犬のさんしょが「おかあさん、あたしゃも、もう17歳になりました。もう直ぐ会えるね。」に泣かされた。自然と食と年月が、無性に切なくなる話でした。2024/09/22
たまきら
37
あれ、ジュリー…?でもこのタイトルって水上勉さんのあれ…?手に取って納得、映画になるんですねえ、ツトムさん。そういえばセクシーなおじいちゃまでした。でも、ここでは映画的な部分よりも料理の部分がとても面白かったです。特に、担当された土井さんの凛とした姿勢が好き。「芋を白く煮るか、黒く煮るか」という言葉に、この人が真摯に食に向き合っていることが伝わってきました。映画にはたくさん土井さんの器や布が使われているようで、鑑賞したくなりました。2022/11/05