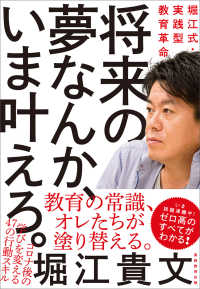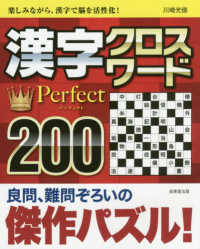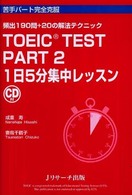出版社内容情報
当代一の影絵師・富右治に大店から持ち込まれた奇妙な依頼とは(「化物 燭」)。越してきた夫婦をめぐって、長屋連中はみな怖気を震うがその正体は?(「隣の小平次」)。名手が江戸の市井を舞台に描く、切なく儚い七つの大江戸奇譚集。
内容説明
当代一の影絵師・富右治に大店から持ち込まれた奇妙な依頼「化物〓燭」。長屋に越してきた若夫婦の男は幽霊だと恐れられるが…「隣の小平次」。付喪神が見える修繕屋の乙次は怪事件に巻き込まれる「夜番」。江戸の市井を舞台に、名手が描く七つの奇譚。
著者等紹介
木内昇[キウチノボリ]
1967年東京都生まれ。出版社勤務を経て、2004年『新選組 幕末の青嵐』でデビュー。09年第2回早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞、11年『漂砂のうたう』で第144回直木賞、14年『櫛挽道守』で第9回中央公論文芸賞、第27回柴田錬三郎賞、第8回親鸞賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たっくん
74
花の散ろ頃、長屋に越してきた若夫婦、夜着の間に衝立が置かれる奇怪な様(隣の子平次)漆商下総屋番頭格佐吉は母のためこおろぎ橋袂の薬種屋に向かう。「補陀落渡海いうことをご存じですか」と店の主人(こおろぎ橋)両国橋西詰豆腐屋「豆源」、豆腐作りの名人「お柄杓」お由のもとに老爺が来て(お柄杓)幼馴染のおのぶとお咲は本両替町油問屋丹波屋に奉公にあがる・・「この子はあんたの疫だ」と女中頭(幼馴染み)「影や道りく十三夜の牡丹餅 さあさ踏んでみいしゃいな」影絵師のもとに奇妙な依頼が(化物蝋燭)他、江戸を舞台の怪談短編集。2024/08/07
piro
45
江戸の奇譚7編。幽霊の類が多く出てきますが、怪談の様な怖さはなく、寂しくもほっと温かくなる話が殆ど。何かしらの心残りを遂げようとする彼岸の人、思いに寄り添う此岸の人。つれあい、親子、きょうだいなど、彼方此方の境界を越えて相手を思う気持ちがじんわり沁みる一冊でした。市井の人々の暮らしと人情が生き生きと描かれるのも木内作品の魅力。幾つかの作品で描かれる職人気質も江戸らしくて良いなぁ。『蛼橋』、『お柄杓』が特に良かったです。唯一『幼馴染』だけは怖さを感じた作品。結局生身の人間が一番怖いということか…。2023/01/21
papako
42
アンソロジーで読んだ一編がずっと気になっていた短編集。怪談なんだけど、怖いよりも切なさや人の情などが迫ってきましたた。『幼馴染』だけは読み始めて嫌な予感しかなくて無理でしたが、あとは全部好き。それぞれ味わいが違って楽しめました。お気に入りは『お柄杓』2人は添ったんですよね。彼女の作る木綿豆腐食べてみたい。表題作のまとめ方も好き。『夜番』鍋みたいってどんなシワ?この作者さん2冊目ですが、他のも読んでみたい。2024/09/29
エドワード
40
江戸の長屋でつましく暮らす人々が出会う不思議。大切な人を亡くした者の、悲しみを心に秘めた静かな日々。密かに慕う兄嫁を亡くした宗次郎。妻と娘を亡くした絵師の窪幾英。生まれ変わった妻を一目見たさに、時をかける孫六。妹の姿を見守る、正真の幽霊・平蔵。幼馴染みの残酷さを描く掌編が怖い。標題作はその名の印象ほど怖くない。むしろ親子の機微が心にしみる。舞台となる豆腐屋、漆屋、和菓子屋、油問屋などの細やかな描写、江戸言葉の歯切れ良さ。蝋燭の炎。下駄の鼻緒。姉様絵。随所に描かれる江戸の情緒。得も言われぬ美しさを感じる。2022/07/04
Y.yamabuki
27
怖いのは苦手だけれど、これは丁度いい塩梅。むしろこの世の人間の方が怖かった。この世に姿を現すのは、何かしら、訳が有ってのこと。それらは、温かかったり、切なかったり、悲しいけれど優しかったり。章立ての妙で、しんみりした後にほっと出来る温かい話で一息付く。江戸っ子らしい歯切れの良い台詞まわしと軽妙な文章が心地好い。2022/08/23