出版社内容情報
最愛の娘を殺した母親は、私かもしれない。刑事裁判の補充裁判員になった里沙子は、子どもを殺した母親をめぐる証言にふれるうち、いつしか彼女の境遇にみずからを重ねていくのだった--。社会を震撼させた乳幼児の虐待死事件と〈家族〉であることの光と闇に迫る心理サスペンス感情移入度100パーセント、『八日目の蝉』『紙の月』につづく、著者の新たな代表作が、いよいよ文庫化!
内容説明
刑事裁判の補充裁判員になった里沙子は、子供を殺した母親をめぐる証言にふれるうち、彼女の境遇に自らを重ねていくのだった―。社会を震撼させた乳幼児の虐待死事件と“家族”であることの光と闇に迫る、感情移入度100パーセントの心理サスペンス。
著者等紹介
角田光代[カクタミツヨ]
1967年神奈川県生まれ。90年「幸福な遊戯」でデビュー。96年『まどろむ夜のUFO』で野間文芸新人賞、2003年『空中庭園』で婦人公論文芸賞、05年『対岸の彼女』で直木賞、06年「ロック母」で川端康成文学賞、07年『八日目の蝉』で中央公論文芸賞、11年『ツリーハウス』で伊藤整文学賞、12年『紙の月』で柴田錬三郎賞、同年『かなたの子』で泉鏡花文学賞、14年『私のなかの彼女』で河合隼雄物語賞を受賞。現在、『源氏物語』の完訳に取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
382
本書はその三重構造に特質を持つ。すなわち、被告の水穂がいて、その水穂に引き寄せられていく里莎子がいる。そして、その里莎子に半ば感情移入しながら投入して行く読者という意味での三重構造である。その意味では、作者の側からすればこれまでにあまりないタイプの手法であり、一方の読者の側からすれば享受の仕方ということになるだろう。里莎子の混乱と困惑はすなわち読者が感じるそれとして引き受けられるのである。そうだとすれば、本作はかなりな割合の読者(とりわけ同性の)から共感を持って迎えられるだろう。2024/12/15
のり
191
幼児虐待死事件の裁判員になった「里沙子」も幼い子を持つ身。子育ての多忙・苦難は自身に置き換えても経験中。周りの人の言動にも過剰に反応し殻に閉じ籠る。状況によって同じ言葉や接し方も、別の捉え方をする時がある。誰にも頼れない苦しさは想像を絶する。被告人の真意は何処に…本作は性別を問わず訴えてくる。思い当たる事も多々ある。このような痛ましい事件は本当に辛い。2020/02/25
エドワード
181
日本は、何と子供を育てにくい国なのだろう。イクメンと言う言葉が流行るのは、仕事に囚われ育児をしない父親が圧倒的に多いことの裏返しだ。古い価値観に固執する両親の圧力、夫婦間の微妙な力関係、母親を孤独に追いやる要素ばかりだ。二歳の娘を持つ専業主婦の理沙子が、幼女を風呂で溺死させた若い母親の裁判の補充裁判員に選ばれた。公判の度に、娘を義父母に預けて出席する理沙子は、微細にわたり進められる審理の中で、次第に被告に自分を重ねていく。<私も同じ経験をした。>理沙子の心の描写が迫力満点、これも家族の姿。希望のある終幕。2018/12/29
JKD
151
自分が我慢していることに誰も気づいてくれない苛立ち。自分は間違ってないことをしているつもりなのに周囲から間違っていると思われてしまう嫌な感覚。みんなは一般的な立場で物事を言っているのに、実際はそんな思うようにいかないといった当事者にしかわからないことが相手に伝わらないという苛立ち。真面目さゆえの気張りすぎ、考えすぎ、気にしすぎが負のスパイラルを増幅させていく。日常会話での些細なズレが不安あるいは不快になるという微妙な感覚がヒシヒシ伝わりました。2018/12/30
nanako
150
久しぶりにつらい、苦しい読書でした。最初は中々頁をめくる手が進まず、途中で読むことをやめようか…とも思いましたが、どうしても結末が知りたくて、最後まで読み通しました。言いたいであろうことは、よくわかるんです。でも、最後まで読み通しても、最初の「つらい、苦しい」という印象が変わることはありませんでした。2020/06/14
-
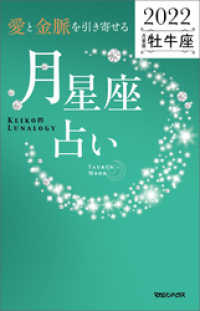
- 電子書籍
- 愛と金脈を引き寄せる 月星座占い202…








