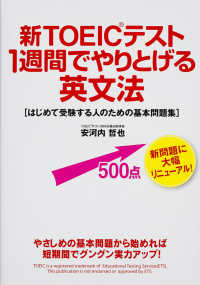内容説明
能、狂言、茶道、絵画などが勃興し、現在の日本文化の原点といえる室町の世を考えながら早春の京都・紫野を歩いた「大徳寺散歩」。大燈・一休以来の厳しい禅風がいまも生きる境内を、心地よい緊張感を感じつつゆく。「中津・宇佐のみち」では、宇佐使の宇佐八幡、黒田官兵衛の築いた中津城と、歴史をたどる。そして幕末の中津が生んだ福沢諭吉の、独立不羈の精神について多く筆を費やす。
目次
大徳寺散歩(紫野;高橋新吉と大徳寺;念仏と禅;真珠庵 ほか)
中津・宇佐のみち(八幡大菩薩;みすみ池;宇佐八幡;宇佐の杜 ほか)
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。主な作品に『竜馬がゆく』、『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの跫音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
57
2014.01.22(01/22)(初読)司馬遼太郎著。 01/21 (地元、宇佐から先に読みます-i-miya) ◎八幡大菩薩。 八幡(はちまん)といいやはたという。 いずれも八幡神(はちまんしん=やはたのかみ)のことである。 この神はもっともはやい時代に仏教に習合したから「八幡大菩薩」などという。 日本の津々浦々に多い神々といえば、天神(天満)さんに八坂神社、それに御稲荷さんだが、わが八幡宮はそれらを超えて全国四万余社ある。 2014/01/22
Book & Travel
42
大徳寺散策に合わせて購入。大燈国師から一休や沢庵といった個性ある名僧、更に利休や遠州など大徳寺に纏わる多くの人物と出来事について、膨大な知識に基づいて深く掘り下げられ、これ一冊で散策の楽しさが大きく増した。世俗を寄せ付けない厳しい禅風を持ちながら、なぜ多くの権力者の支持を得たのか解り、興味深かった。中津・宇佐の方は馴染みのない地域だが、八幡宮の総本社・宇佐八幡宮、黒田如水や細川忠興が整備し福沢諭吉が育った中津と、話題豊富で飽きさせない。特に道鏡の宇佐八幡宮神託事件の掘り下げ方と、城井谷の悲劇が興味深い。2016/08/22
kawa
37
コロナ禍、月末または月初は「街道をゆく」が恒例化。グーグル・マップも駆使してリモ-ト+誌上旅に。で、今月は俗化を拒み静けさを守る大徳寺と、道鏡の皇位を巡る偽神託事件で有名な宇佐神宮を中心とする中津・宇佐のみち。「禅は天才の道で、なまなかな人間がやるとかえって毒」が持論の司馬先生。大徳寺の確かな禅匠・戸田義高氏からその話題を振られると「いや、そのことは他日。・・・・・・」の司馬先生に可笑しみ。直前に読んだ「風よあらしよ」の主人公・伊藤野枝の前夫・辻潤の話題が出てくることにもびっくり。 2021/07/02
金吾
20
大徳寺の話も面白かったですが、宇佐・中津はより面白かったです。特に宇佐八幡の話と如水、宇都宮氏の話はお気に入りです。2021/03/18
はちこう
18
京都大徳寺へ。どういう展開になるのだろうと思って読み進めると、一休さんから千利休の話し、更には細川忠興の話しなどに広がる。大徳寺で多くの歴史が生まれ、それらの歴史が時間軸の上で繋がっているところが面白いと思う。後半で九州、中津へ。その前半は宇佐八幡がメイン。中でも「道鏡事件」は興味深い。司馬さんの既読本でも道鏡のことは書かれていたはずだが、今回はより仔細に書かれていると思う。道鏡の策略を阻止した和気広虫と弟の清麻呂。この二人の名は記憶に留めなければ。須田画伯の挿絵も良い。2024/08/30
-

- 電子書籍
- K.I.R.I.Nキリン~社畜の俺が逃…
-
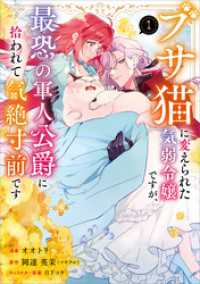
- 電子書籍
- ブサ猫に変えられた気弱令嬢ですが、最恐…