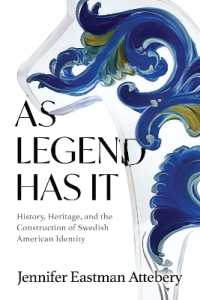内容説明
韓国南端の済州島を、そこを故郷に持つ在日の畏友二人を先達に歩く。日本に押し寄せた蒙古軍が馬を肥やした漢拏山麓の草原をめぐり、巫人や海女など古層で日本文化とつながる民俗を訪ねる。繰り返し表れるのは、朝鮮史五百年の停滞をもたらした科挙および朱子学への強い批判と、巻き込まれざるを得なかった民衆への哀憐の情。著者による朝鮮(民族)論の集大成の観がある一冊。
目次
耽羅紀行(常世の国;焼跡の友情;俳句「颱風来」;三姓穴;塋域の記;石と民家;“国民”の誕生;郷校散策;士大夫の変化;北から南への旅;父老とカプチャン;神仙島;モンゴル帝国の馬;森から草原へ;お札の顔;朝天里の諸霊;不滅の風韻;思想の惨禍;車のはなし;故郷;虎なき里;憑きものの話;近くて遠い;シャーマン;泉靖一氏のこと;赤身露体;『延喜式』のふしぎ)
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。主な作品に『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの跫音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
molysk
59
朝鮮半島の南海に浮かぶ、済州島。古名を耽羅というこの島を旅する。ある国の古い文化は、移り変わりの早い中心ではなく、しばしばその周縁に姿をとどめるものである。李氏朝鮮では、儒教の学派である朱子学が盛んであった。年長者を敬い、親に孝行を尽くすといった道徳は、司馬が旅した済州島には色濃く残っていた。江戸幕府は朱子学を重んじるも、支配者の学問にとどまり、民衆への広がりは見られなかった。儒教の影響で官僚による教条的な統治がなされた朝鮮と、儒教が根付かずに武士が実学的な支配をおこなった日本を、司馬は対比させる。2023/12/23
kawa
39
2月締めは耽羅(たんら/韓国・済州島)編。司馬先生の〈朱子学というドクマで文明を故意に停滞、世界史的にも稀有な500年不動を維持した李氏朝鮮〉の蘊蓄のアレコレに興味あり、が、理解に?…のところ、「国が小さい、人口が少ないが『老子』の理想郷」(210~211頁)の記述でナルホド納得。続編的に描かれる神おろしの巫人(ふじん)と海女の話等も面白い。特に、シベリア、モンゴル、満州、朝鮮、日本は古層として文化を共有、済州島の巫女や日本の神道もその共通する文化に存するシャ-マニズムから派生しているとの記述は印象的。2021/02/28
かず
25
耽羅とは韓国 済州島にあった古代国家。1985年10月から12月にかけて、友人の在日知識人と島内を巡る。例え不愉快な事柄に遭遇しようとも、努めて相手を理解しようと徹する先生に脱帽する。先生は韓国人の反日感情の根源に李氏朝鮮時代以来の朱子学の呪縛に見る。朱子学に限らず、儒教は、己を君子と規定する以上、他者を取るに足らないもの(小人)と見下す弊害に陥りやすい。先生はしきりに「誇り高い」とそやすが、私は「誇りとは何か」を真の意味で理解せねば危険であると感じる。自己批判なき誇りは自慰でしかないと思う。2019/02/12
koji
20
街道をゆく18冊目。司馬さんは、古代、耽羅の国と云われた済州島を2回訪ねます。1回目は、漢拏山(ハルラサン)の周囲の町村をぐるりと回り山に登ります。その主題は、李氏朝鮮500年の停滞への深い憤り(ドグマの悲劇、朱子学の惨禍とう激烈な言葉で表現します)と、そこに巻き込まれた民衆への限りない哀惜。ただ、同時にその文化の深さに触れ、心残りを感じた司馬さんは、2回目、同島の巫人、海女に会いに行き、耽羅の人々の一部が日本のルーツになったことを知ります。今まで読んだこのシリーズの中でも、味わい深さでは一、二の傑作です2025/05/15
金吾
18
街道をゆくは司馬さんの知識に基づく好奇心のすごさを感じさせるシリーズだと思いますが、今回も様々な視点で済州島をみていて面白かったです。2020/12/12
-

- 電子書籍
- 玉の輿ゲーム 【分冊版】 10 U-N…