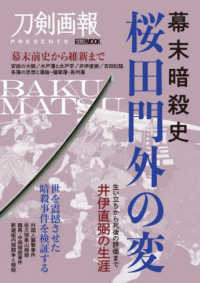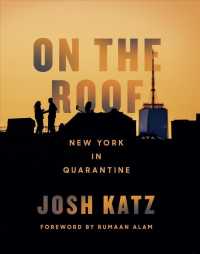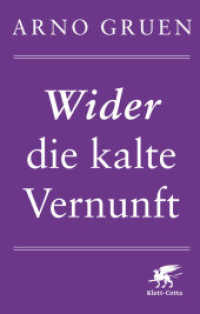内容説明
大航海時代をヨーロッパからの視点で考えたのが『南蛮のみち』であり、中国からの視点で考えたのが『〓(びん)のみち』になる。中国東南部の福建省は古来から「〓(びん)」と呼ばれ、日本とのつながりが深い。マルコ・ポーロが立ち寄った泉州、一大海上王国をつくった鄭成功ゆかりの厦門を訪ねてゆく。筆者の脳裏に、東西交渉史の主役たちが浮かんでは消える。
目次
文明交流の詩情
倶楽部
山を刻む梯田
福州の橋
独木舟
山から山へ
焼畑族
対々の山歌
雷峰を過ぐ
餅から鉄へ
天目茶碗
土匪と械闘
華僑の野と町
異教徒たち
『西遊記』ばなし
陶磁片とコンパス
泉州の出土船
イカリの話し
七百年前の山中さん
夢のアモイ
廈門両天
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。主な作品に『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの跫音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kawa
32
(再読)閔(びん)→福建省(中国南部)。15世紀ヨーロッパの大航海時代に先駆けアラブ、インド、中国による南海航海時代の母港となった泉州等を訪ねる。当時の中国船やアラビア船、果ては元寇の際の船舶事情(第1次は粗末な高麗船、第2次は上等な浙江・福建船)まで司馬先生の蘊蓄が冴える巻。ところで中国南部、雲南省・昆明とラオス・ビエンチャンが鉄道(中国ラオス鉄道)で結ばれたり、広西チワン自治区の区都・南寧から南シナ海を結ぶ134㎞の大運河が建設中。中国から東南アジアの交流インフラが充実、新しい発展地域として注目かも。2023/06/13
kawa
31
びん(門構えに虫・今の福建省)の旅。上海以南は2世紀辺りまでインドシナ諸族の民が暮らす地で、稲作や日本人の祖先もかの地から独木船でやってきた可能性が高いと言う。3世紀以後に、漢民族が入植して中国化が徐々に進み、12世紀前後には福州を中心に世界的国際都市として繁栄していたが、明の海禁政策以降、文明の発展に乗り遅れていった歴史の興亡を追う旅。巻末で触れる、漢族というもの自体、その存在がなかったのではないかと言う司馬先生の考えもなるほどと思う。2020/11/03
aponchan
22
司馬遼太郎氏の作品乱読中のうちの1冊。中国・閩のみちとはどこなのだろうと思い、読み始めた。中国が多種多様な民族国家であって、南の方面は夷として見られていたことは、他の司馬氏の著作を以前に読んで知ったが、イスラム教徒との交流や関係性、台湾や日本との歴史的な関係という観点で知ることができたのは良かった。 書かれたころとは、都市化も進み、今は大分雰囲気も変わっているだろうが、底流に流れているものは同じなのだろうと思いながら本書を読めたことは良かった。引き続き、司馬氏の著作は読んでいきたいと思う。2020/04/25
はちこう
15
昔、福建省(閩)は百越の一地域だった。日本との交流も盛んだった。今回は、泉州の博物館の出土船を見るのが目的の一つだったらしい。出土船の画像をネットで見る。その造船技術の高さを感じる。マルコ・ポーロの東方見聞録の頃、泉州港は世界最大の貿易港だった。しかし、明は海禁(鎖国)を打ち出し世界史から大きく後退する。その結果、倭寇が生まれ、さらには王直が活躍するのだから、この海禁は色々な意味で日本史に大きな影響を与えたと言えそう。福建省と日本の歴史的な繋がりのようなものを感じた。2024/02/03
紫羊
15
中国の福建省を巡る。日本とのつながりなど興味深い話が満載だった。2021/08/16
-
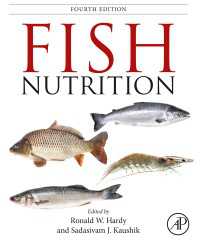
- 洋書電子書籍
-
魚類栄養学(第4版)
Fish …
-
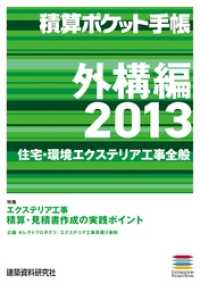
- 電子書籍
- 積算ポケット手帳 外構編2013