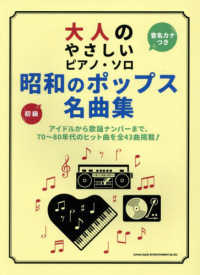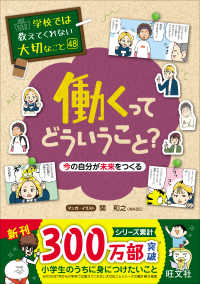内容説明
島原の乱(1637年)が大きなテーマになっている。島原半島を歩き、戦場の原城跡で思索を重ねる。親子二代で暴政を敷いた島原領主、松倉重政・勝家親子については「ごろつき」と容赦がない。一揆に強い同情を持ちつつ、無理やり参加させられた人々のことも忘れない。天草・本渡では延慶寺の樹齢500年の梅に魅せられる。夜の闇にうかぶ梅の花の描写が幻想的だ。
目次
松倉重政
城をつくる
がんまつ
サン・フェリペ号の失言
沖田畷の合戦
明暗
侍と百姓
南目へ
北有馬
口之津の蜂起〔ほか〕
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
1923年、大阪府生まれ。大阪外事専門学校(現・大阪大学外国語学部)蒙古科卒業。60年、『梟の城』で直木賞受賞。75年、芸術院恩賜賞受賞。93年、文化勲章受章。96年、死去。主な作品に『国盗り物語』(菊池寛賞)、『世に棲む日日』(吉川英治文学賞)、『ひとびとの蛩音』(読売文学賞)、『韃靼疾風録』(大佛次郎賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
むーちゃん
117
ちょうど1ヶ月半程前(10月下旬)に島原、五島列島に母親と旅行へ行きました。 その後に読んだせいか、はたまた実家の佐賀に近いこともあるのか興味深く読んだ。原城に行った際には、文中にも出てくるように当時の惨劇が甦ってくるかのような錯覚すらおぼえた。 この本で、切支丹のこと、島原、天草についてもっと知りたく、かつまた訪れたい場所も増え再訪したい気持ちも強まった。 2019/12/12
Book & Travel
54
今年、長崎と天草の切支丹関連遺跡が世界遺産に登録された。本書の旅は40年近く前。司馬さんが訪れた原城と崎津集落は世界遺産になっている。家康亡き後、広い視野と判断力も無く異端者をただ恐れ取り締まる三代目政権と、それに追従する領主・松倉が招いた島原の乱。苛烈な搾取と拷問に虫酸が走る一方、切支丹でない農民も乱への参加を強要され殺されたというのもやりきれない。天草の隠れ切支丹が、明治後派遣された本当の神父に、信仰内容が違いすぎて戸惑い隠れ続けたという話も印象的。健気で切なく、信仰というものを改めて考えさせられた。2018/08/08
kawa
39
冒頭から肥前島原領主・松倉重政を「(彼ほど)忌むべき存在はない」と非難することによって始まる「島原の乱」の旧跡を中心にめぐる旅。乱は切支丹による殉教的一揆ではなく、領主の圧政に追い詰められた農民の絶望的な反乱であるとする司馬先生の見解になるほど初知り感心。電子書籍で積み読となっている遠藤周作氏の「沈黙」を読み始める動機にもなりそう。レベルの低い認識で恐縮ながら、島原は長崎県、そこと経済・文化的に近い天草が熊本県も初知り。こちらも行って見なければいけないと意欲高まる地だ。2020/05/13
aponchan
32
司馬遼太郎氏作品乱読のうちの一冊。とても時間がかかりましたが、高校生の時に修学旅行で訪れた時の情景を断片的に思い出しながら読んだ。当時はキリシタン弾圧や天草四郎の誤った固定概念を通して島原城等を見ていたので、再度、訪れてみたいと思った。 江戸幕府の為政は見事なまでの情報操作でコントロールできた事例かとある種、感心した。表紙の写真が本当に良かった。 2021/11/15
ぐっち
26
出身地をいうと高確率で「島原の乱の?」と聞かれる私。「街道をゆく」に島原・天草があると知り、読んでみました。司馬遼太郎先生が、めっちゃ島原の人に肩入れしてる!しかも住みたいとまで褒めちぎってる!と喜んだのもつかの間、天草に渡ったら天草のほうが明るいだと…?ともあれ原城はいまだに何もないけど、崎津教会めっちゃ素敵だし、海の幸山の幸に温泉にイルカウオッチングもできるので島原・天草編の聖地巡礼流行らないかな~と思いました。2025/11/04
-
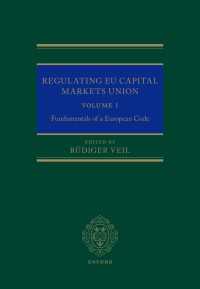
- 洋書電子書籍
- EUにおける資本市場同盟規制(全2巻)…
-

- 和書
- 詳解物理学演習 〈下〉